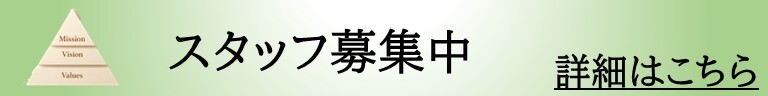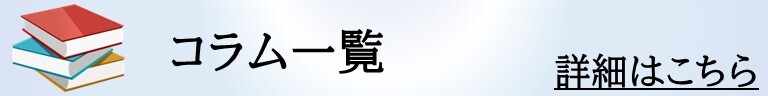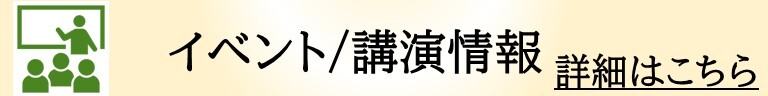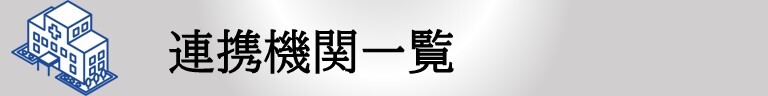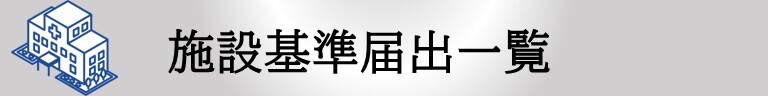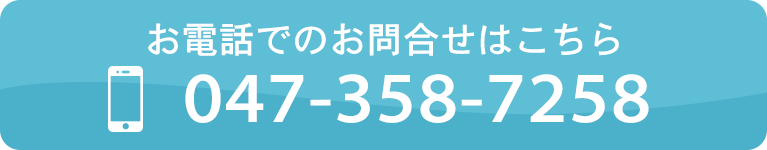認知症の方を自宅介護するときの注意点と負担を軽減する方法
「認知症の家族を自宅介護したいけど不安を感じる」「注意点があれば教えてほしい」などと考えていませんか。専門的な知識がないため、困っている方は多いでしょう。認知症患者さんの自宅介護には、住み慣れた環境で療養生活を送れるなどのメリットがあります。一方で、ご家族の負担が大きくなりやすい点にも注意が必要です。ここでは、認知症患者さんを自宅介護するメリット、デメリットと自宅介護の注意点、自宅介護の負担を軽減する方法などを解説しています。今後について検討を進めている方は参考にしてください。
認知症の主な症状
認知症は、脳の病気で認知機能が低下し、社会生活に支障が生じた状態です。症状は中核症状と周辺症状にわかれます。主な症状は中核症状の認知機能障害です。具体的な症状として以下のものがあげられます。
| 認知機能障害 | 概要 |
|---|---|
| 記憶障害 | 新しいことを覚えられなかったり、覚えたはずのことを思い出せなかったりする |
| 実行機能障害 | 計画を立てたり、順序だてて物事を行ったりすることが難しくなる |
| 見当識障害 | 時間や場所、人物などがわからなくなる |
| 言語障害(失語) | 話したいことを言葉にできなかったり、言葉の理解が難しくなったりする |
| 失行 | ある目的の行動を適切に行えなくなる(歯ブラシを正しく使えない、一人でトイレを正しく使えないなど) |
| 失認 | 対象を正しく認識できなくなる(針のある時計を見ても時間がわからないなど) |
障害されやすい認知機能は、認知症の原因で異なります。これらに加えて、周辺症状として、幻覚、抑うつなどの精神症状、徘徊、興奮などの行動異常が現れることもあります。
自宅介護とは?
認知症患者さんを、自宅介護したいと考えるご家族もいます。自宅介護とは、介護施設を利用せず、自宅で介護を行うことを指します。一般的には「在宅介護」と呼ばれています(本記事では自宅介護と記載しています)。具体的な介護の方法はケースで異なりますが、ご家族が行う介護と介護保険の居宅サービスを組み合わせるケースが多いでしょう。つまり、介護施設を利用せず、必要に応じて居宅サービスを活用するケースが一般的です。居宅サービスの例として、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーションなどがあげられます。自宅介護にはメリットとデメリットがあるため、詳細を理解してから選択することが大切です。
認知症の方に対する自宅介護のケア内容
認知症患者さんに対する自宅ケアの内容はケースで異なります。同じ認知症であっても、症状の現れ方や身体の状態には個人差があります。その上で、掃除、洗濯、料理、買い物、金銭管理、服薬管理、スケジュール管理など、手段的日常動作のサポートが求められるケースが多く見受けられます。また、食事、排せつ、着替え、入浴、整容など、基本的日常生活動作のサポートを必要とすることもあります。
ケアのポイントは、認知症患者さんを見守って、行動をサポートしたり環境を整えたりすることです。例えば、トイレの場所がわからない場合は、床にテープを貼って道順を示したり、ドアに目印を貼って場所を示したりすると、移動しやすくなります。認知症患者さんの観察を通じて、精神状態を把握することも重要なケアの一環です。
また、認知症患者さんの中には、不調を言葉で伝えることが難しい方もいます。したがって、体調管理や健康管理も、自宅介護において重要な取り組みの一つです。
認知症の方を自宅介護するメリット
自宅介護には、さまざまなメリットがあります。主なメリットは以下の4点です。
本人とコミュニケーションが頻繁に取れる
自宅介護の主なメリットして、認知症患者さんとご家族がコミュニケーションを図りやすいことがあげられます。これまでと同じ自宅などで生活を継続するためです。また、日常生活をサポートする中でもコミュニケーションを図れます。例えば、入浴中に洗えていない体の部分を伝える、背中をさすりながら、認知症患者さんの反応を観察することなどが挙げられます。
施設介護を選択すると、ご家族にとって都合のよい日時にコミュニケーションをとれないことがあります。各介護施設が、原則として面会時間を定めているためです。仕事の都合で、認知症患者さんに頻繁に会えない場合もあります。認知症患者さんとコミュニケーションを図りやすい点は自宅介護の魅力です。
住み慣れた場所で生活ができる
認知症患者さんが、これまで通りの環境で生活を継続できる点も自宅介護のメリットです。認知症患者さんは、認知機能が低下しているため、環境の変化にうまく適応できないことがあります。環境の変化によるストレスで、認知症の症状が悪化する可能性もあります。具体的には、せん妄や徘徊などが現れやすいといえるでしょう。自宅介護であれば、これまで通りの環境で生活を継続できるため、環境の変化に戸惑うリスクは低くなります。認知症患者さんの不安を軽減できる点も自宅介護のポイントです。
最期まで側にいたい家族の思いが叶う
ご家族の中には、認知症患者さんの側でできるだけ長く過ごしたいと考える方もいます。自宅介護は、このような希望を実現できる可能性がある選択です。環境を整えることで、自宅で看取りを行うことも可能です。認知症患者さんと最期まで一緒に過ごしたいと考えるご家族にとって、大きなメリットとなる介護方法と考えられます。ただし、施設介護に比べると、ご家族にかかる負担は大きくなるので、この点も踏まえて、検討を進めることが大切です。
費用を抑えることができる
自宅介護は、介護費用も抑えられる傾向があります。公益財団法人生命保険文化センターが発表した『2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査』によれば、介護を行った場所別の介護費用(公的介護保険サービスの自己負担費用を含む)は以下の通りです。
| 介護を行った場所 | 介護費用(月額) |
|---|---|
| 在宅 | 4.8万円 |
| 施設 | 12.2万円 |
出典:公益財団法人生命保険文化センター「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」
https://www.jili.or.jp/files/research/zenkokujittai/pdf/r3/2021honshi_all.pdf
具体的な介護費用は状況によって異なりますが、自宅介護は費用を抑えやすい傾向があります。
認知症の方を自宅介護するデメリット
自宅介護には、デメリットもあります。主なデメリットは以下の2点です。
介護者の負担が大きい
自宅介護を始める前に理解しておきたいのが、ご家族など、介護を担う方にかかる負担です。具体的な負担は状況によって異なりますが、認知症患者さんの状態によっては大きな負担が生じることがあります。介護のために仕事を休む必要が生じたり、睡眠時間が不足したりする場合があるためです。1人で頑張ると、介護疲れで倒れてしまうこともあります。ご家族で協力できる体制をつくる、必要に応じて介護サービスを利用するなど、対策を講じておくことが大切です。
認知症の正しい対応知識が必要
自宅で介護を行う場合、認知症に対する正しい理解が求められます。認知症患者さんの言動や行動には理由があるためです。理解が不足していると、本人の意図を把握できず不都合な行動と捉えて、対立してしまうことがあります。理由もわからないまま、言動や行動を制止された認知症患者さんは傷ついてしまうでしょう。介護する方が適切に対応することで、認知症患者さんが穏やかな生活を送る助けとなる場合があります。一定の知識が求められる点も、自宅介護を始める前に理解しておきたいポイントです。
認知症の方を自宅介護する際の注意点
続いて、自宅介護の注意点を解説します。
症状を理解する
自宅介護を行うために、認知症に対する理解が欠かせません。認知症患者さんは、記憶障害や見当識障害などの影響で、これまでできていたことができなくなったり、理解していたことがわからなくなったりする場合があります。これに加え、周囲の環境や認知症患者さんの性格が影響し、さまざまな出来事が生じることがあります。
認知症について理解を深めておけば、言動や行動の背景を捉えて、適切に対応できることがあります。例えば、認知症患者さんが自宅内を目的もなく歩き回る場合を考えます。「危ない」「邪魔」と捉えてしまうかもしれませんが、行動の背景に家族の役に立ちたいという想い(想いはあるが何をすればよいかわからない)があるかもしれません。このようなケースであれば、行動を制限せず、声をかけて家事を手伝ってもらうことで、双方にとってより良い生活環境を整えることが可能です。
本人の意思を尊重する
認知症患者さんの意思、存在を尊重することも大切です。できないことやわからないことが増える認知症ですが、自尊心が失われるわけではありません。本人の意思や存在を無視して対応すると、相手を深く傷つけてしまう恐れがあります。例えば、子ども扱いして本人がやろうとしていることを否定する、間違いを指摘して怒鳴りつけるなどすると、本人を混乱させてしまったり悲しませてしまったりすることが考えられます。信頼関係が損なわれることもあるでしょう。認知症患者さんを1人の人間として尊重しつつ、自宅介護を行うことが大切です。
健康管理に気を配る
認知症患者さんは、自分のことを言葉でうまく表現できないことがあります。体調不良をうまく伝えられないこともあるでしょう。したがって、介護をする方が健康管理に気を配る必要があります。日常生活で気をつけたい主なポイントは以下の通りです。
【健康管理で気を付けたいポイント】
- 食事をとっているか
- 水分をとっているか
- 排泄に問題はないか
- 熱は出ていないか
- 顔色や肌の調子はよいか
- お薬を適切に服用できているか
調子が悪いときは、かかりつけ医に相談しましょう。
コミュニケーションを工夫する
コミュニケーションの取り方も気を付けたいポイントです。認知症が進行すると、できることや理解できることが減っていきます。例えば、歯ブラシの使い方がわからなくなることもあります。理解力が低下すると、言葉で使い方を説明してもうまく伝わらないことが少なくありません。このようなケースでは、いつも歯磨きをしている場所へ連れて行ったり、歯磨きしているところを見てもらったりすると、歯ブラシを使えるようになることがあります。認知症患者さんが理解できる方法で、コミュニケーションをとりましょう。
認知症の方とコミュニケーションをとるコツ
ここからは、認知症患者さんとコミュニケーションをとるコツを解説します。
耳元でゆっくりと話す
認知症患者さんの中には、耳が聞こえにくくなっている方もいます。この点を踏まえて、耳元でゆっくり、はっきりと話すことが大切です。また、できるだけ穏やかな口調を心がけましょう。話を聞きとれなかったり、激しい口調で話しかけられたりすると、不安を感じる方がいるためです。
「話しても理解できないから話さない」といった姿勢にも注意が必要です。コミュニケーションが不足して、両者の信頼関係を損ねてしまう恐れがあります。認知症患者さんの不安を少しでも取り除くため、耳元でゆっくり、はっきりと話しかけるようにしましょう。
否定せずにまずは受け止める
認知症患者さんと話をしていると、会話がかみ合わないことがあります。「間違えている」などといいたくなるかもしれませんが、頭ごなしに否定することはおすすめできません。認知症患者さんにとっては、覚えていることが事実であり、覚えていないことは事実ではないと認識されているためです。客観的な事実だけにこだわると、本人を混乱させてしまったり、対立を生んでしまったりする恐れがあります。命にかかわるなどの大きな問題がなければ、認知症患者さんの話を受け入れるとよいでしょう。本人が過ごしている世界を理解できたり、信頼関係を構築できたりします。
共感する
認知症患者さんに共感を示すこともコミュニケーションのコツです。共感は、相手の感情や考えに間違いないと感じることと説明できます。したがって、共感を示すと、認知症患者さんが安心感を抱きやすくなります。また、信頼関係も構築しやすくなるでしょう。共感を示す方法として、相手の話を傾聴したり、肯定したりすることがあげられます。例えば、相槌を打って話を促す姿勢を示したり、「素晴らしいですね」「それは良かったですね」などの言葉で肯定することが考えられます。
短い言葉で話す
認知症患者さんは、複雑な話を理解しにくくなっていることがあります。自分本位なコミュニケーションを図ると、混乱させてしまうことがあるため注意が必要です。できるだけ短い言葉で話すなど、認知症患者さんにとってわかりやすいコミュニケーションを心がけましょう。例えば、1つの文章に含まれる質問を1つだけにする、「Yes/NO」で応えられる質問にする、会話の内容を具体的にするなどが考えられます。
ジェスチャーを交えて話す
コミュニケーションの方法は、大きく以下の2つにわかれます。
| コミュニケーションの方法 | 概要 |
|---|---|
| 言語的コミュニケーション | 言葉を用いたコミュニケーション方法 |
| 非言語的コミュニケーション | ジェスチャーや表情、動き、声のトーンなどを用いたコミュニケーション方法 |
非言語的コミュニケーションを活用すると、言葉の理解が難しい認知症患者さんとも効果的なコミュニケーションを図れます。特に、アイコンタクトを取ることは重要です。にこやかな表情で相手の目を見て話しかけるだけで安心感を与えられます。身振り、手振り、表情などを活用しつつ、コミュニケーションを図りましょう。
怒ったり命令したりしない
認知症患者さんを自宅で介護していると、予想外の行動をされて怒りたくなったり、コミュニケーションをうまく取れずに命令したくなったりすることがあるはずです。仕方がないと感じる場面もありますが、頭ごなしに怒ったり、相手の意思を尊重せずに命令することは避けるべきです。認知症患者さんが状況を理解できずに、傷ついてしまったり、心を閉ざしてしまったりすることがあります。不信感や不穏な状態につながる可能性があるため、十分な注意が必要です。
表情を観察して気持ちを汲み取りながら話す
認知症患者さんの表情をよく観察していると、そのときの気持ちを理解できることがあります。例えば、戸惑った表情をしていたり、困った表情をしていたりすることがあります。相手の気持ちを察したときに「どうしましたか?」「何かお困りですか?」などの声かけを行うと、認知症患者さんの気持ちに寄り添いつつ理解を深められます。表情や態度などを観察することも、認知症患者さんとコミュニケーションをとるコツです。
認知症の方の自宅介護に限界を感じてしまう理由
認知症患者さんを自宅介護しているご家族の中には、限界を感じる方もいます。どのような理由で限界を感じることが多いのでしょうか。
精神的な負担
自宅介護のメリットは、認知症患者さんの側で過ごせることです。一方で、介護サービスを利用していないときなどは、認知症患者さんに気を配らなければなりません。自分の時間をとれずにストレスが溜まることや終わりが見えない自宅介護に疲れてしまうことがあります。また、認知症患者さんの行動や言動を理解できず、モチベーションが下がることも考えられます。精神的な負担は、自宅介護に限界を感じる大きな理由です。
身体的な負担
身体的な負担で、自宅介護に限界を感じることもあります。日常生活の介助で体に大きな負担がかかったり、十分な睡眠時間を確保できなくなったりすることがあるためです。例えば、入浴の介助で腰を痛める、徘徊の対応でゆっくり眠れないなどが考えられます。高齢の方は、身体的な負担を特に感じやすいといえます。心配な方は、介護サービスを活用するなどの対策を検討しておくほうがよいでしょう。
金銭面の負担
一般的に、自宅介護は施設介護よりも費用がかかりにくいと考えられています。しかし、介護用品を購入したり、住宅を改修したりすると、まとまった費用がかかります。金銭面の負担が重いと感じることは少なくありません。また、状況によっては、介護離職を選択しなければならないこともあります。収入が減ると、金銭面の負担感が増すでしょう。お困りの場合は、介護保険サービスの自己負担額を抑えられる高額介護サービス費などを活用するとよいかもしれません。
認知症の方の自宅介護の負担を軽減させる方法
自宅介護の負担感は、いくつかの方法で軽減できる可能性があります。認知症患者さんを自宅介護するときに検討したい対策を紹介します。
専門家に相談する
自宅介護の負担は、専門家に相談すると軽減できる可能性があります。悩みを聞き、活用できる制度を紹介するなど、環境の調整を支援してくれる場合があるためです。参考に、身近な専門家を紹介します。
【専門家の例】
- ケアマネ―ジャー
- 地域包括支援センター
- 認知症の家族会
ケアマネ―ジャー、地域包括支援センターは専門家の視点から、認知症の家族会は介護経験者が同じ介護者の目線からサポートをしてくれます。相談したい内容に応じて、使い分けるとよいかもしれません。
介護サービスを活用する
介護サービスを活用すると、自宅介護の負担を大きく軽減できる可能性があります。ご家族だけで抱え込むと共倒れになる恐れがあるため、積極的に活用したいサービスといえるでしょう。介護サービスは、介護保険サービスと介護保険外サービスにわかれます。前者は保険を適用できるため、自己負担額を1~3割に抑えられます。自宅で利用できる主なサービス(居宅サービス)は以下の通りです。
【居宅サービス】
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
デイサービスやショートステイを利用すると、ご家族が自分の時間を確保できます。介護保険外サービスは、介護保険を適用できないサービスです。費用は全額自己負担ですが、介護保険では対応できないサービスを提供していることが少なくありません。これらのサービスを活用したい方は、ケアマネ―ジャーや地域包括支援センターに相談するとよいでしょう。
補助金制度を利用する
自宅介護を始めると、さまざまな費用がかかります。金銭面の負担が重いと感じる場合は、自治体などの補助金制度を活用するとよいかもしれません。まずは、市区町村の窓口で相談したり、地域包括支援センターの社会福祉士に相談したりするとよいでしょう。医療費用や介護費用が高額になった場合は、高額療養費制度や高額介護サービス費制度を活用できる可能性があります。いずれも医療費用や介護費用の自己負担額を抑えられる制度です。
介護施設への入居を検討する
ご家族の身体的負担や精神的負担が想定していたより重い場合は、介護施設への入居を検討してみてはいかがでしょうか。具体的な選択肢として、特別養護老人ホーム、グループホーム、有料老人ホームなどがあげられます。入居の対象や提供しているサービスなどは介護施設で異なるため、ケアマネジャーに相談して、詳細を確認してから検討を進めることが大切です。罪悪感を抱く場合もありますが、身体的および精神的負担が軽減されることで、認知症患者さんとの関係が改善される可能性もあります。
認知症患者さんの自宅介護は準備をしてから始めましょう
ここでは、認知症患者さんの自宅介護について解説しました。主なメリットは、住み慣れた環境で療養生活を送れることです。認知症患者さんが安心して暮らせると考えられます。ただし、注意点がないわけではありません。日々の生活をサポートするご家族には、身体的、精神的、金銭的負担がかかる場合があります。また、認知症に関する一定の知識も求められます。専門家に相談し、サポート体制を整えるなど、十分な準備を整えてから自宅介護を開始することが重要です。
市川市・浦安市で訪問診療の受診をお考えの方は、
南行徳の面野医院 (訪問診療専用番号 047-321-4600)へご相談ください。