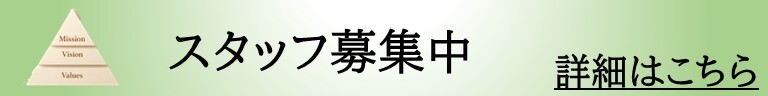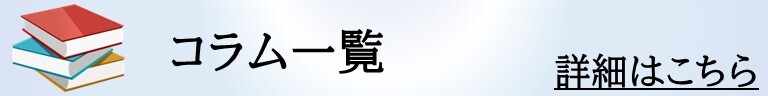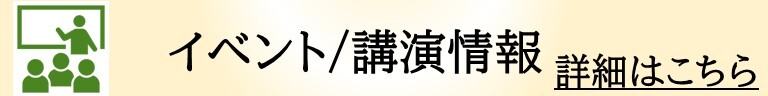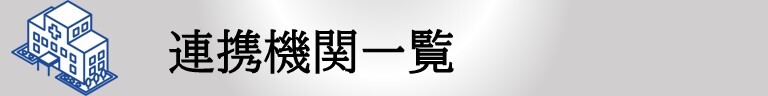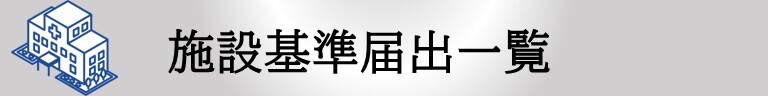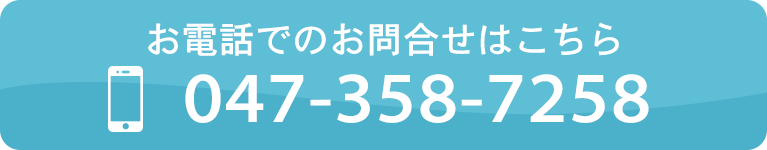施設から在宅医療へ移行が進む理由は?在宅医療のポイントを解説
高齢化社会の進展により、介護や医療は以前より重要なサービスとされるようになっています。特に、高齢の患者が生活の質を高め、快適な老後を送るための取り組みが重要視されています。
高齢者向けの施設には、住宅や共同住宅、介護付きの福祉施設などさまざまな形態があります。一方で、近年は自宅に戻り医療サービスを受ける『在宅医療』を希望する方が増加しています。
この記事では、施設から在宅への移行が増加している理由や在宅介護・在宅医療の利点について詳しく解説します。在宅介護・医療を支えるサービスと制度や移行を検討する際のポイントも取り上げていますので、ぜひ参考にしてください。
施設から在宅へ移行する理由
施設から在宅へ移行する理由として、次の3点が考えられます。
- 高齢者の多くが自宅での生活を希望している
- 医療政策の変遷
- 地域包括ケアシステムの推進
施設から在宅へ移りたいという希望のほかにも、医療にかかわる政策の変遷や地域でのケアが見直されるといった変化が挙げられます。
高齢者の多くが自宅での生活を希望している
内閣府の発表によると、60歳以上の約半数である51.0%が、治る見込みのない病気にかかった際に自宅での最期を希望しています。(※1)
51.0%のうち、男性は59.2%、女性は43.8%と、男性の方が10%以上高い結果となりました。ただし、女性は回答者の年齢が上がるにつれて自宅を希望する割合が増加する傾向が見られます。
さらに、内閣府が発表した『平成27年版高齢社会白書』によると、全国の60歳以上の男女に『介護を受けたい場所』を尋ねた結果、自宅を希望した割合が男性で42.2%、女性で30.2%となっています。(※2)
これらの結果から、60歳以上の高齢者の多くが自宅での介護や最期を希望していることがわかります。このような意識が、施設から在宅への移行を後押しする要因となっています。
※1参照元:内閣府「第1章 高齢化の状況(第3節 1-4)」
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2019/html/zenbun/s1_3_1_4.html
※2参照元:内閣府「平成27年版高齢社会白書(概要版)」
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2015/gaiyou/pdf/1s2s_3.pdf
医療政策の変遷
日本の医療政策は、明治維新以降急速に発展し病院の整備とともに診療所が増加したことで、昭和60年(1985年)には、第1次医療法改正と地域医療計画の創設が行われ、保健医療計画と呼ばれる医療政策の計画化が進められました。(※1)
当時、すでに老人保健法が制定されていたことに加え、翌年には『長寿社会対策大綱』と呼ばれる高齢社会への中長期的指針が策定され、在宅サービスの拡充が検討されました。
2006年には介護保険の改正に伴い、介護予防を重視する方針が打ち出されました。さらに、2012年には在宅医療の充実を図り、機能強化型在宅療養支援診療所・病院の創設が決定されました。(※2)]
これらの変遷を経て、病床数は受け入れる患者の状態に応じて調整されるようになり、在宅診療への注力が方針として明確にされています。
※1参照元:日本医史学雑誌第62巻第2号「医療政策にみる病床数思想の変遷」
http://jshm.or.jp/journal/62-2/62-2_19.pdf
※2参照元:厚生労働省医政局指導課在宅医療推進室「在宅医療の最近の動向」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/dl/h24_0711_01.pdf
地域包括ケアシステムの推進
福祉・介護地域包括ケアシステムとは、団塊の世代が2025年に75歳以上となることを受け、要介護状態であっても住み慣れた地域で生活を続けられるように、住まいや医療などを包括的に提供する仕組みです。
5つの要素には、『住まい』『医療』『介護』『予防』『生活支援』が含まれます。これらの要素を基盤に、病院や診療所、訪問看護事業所などの事業者や機関が連携し、サービスを必要とする高齢者を在宅の状態で支援することを目標としています。(※)
※参照元:厚生労働省「地域包括ケアシステムと在宅医療」
https://www.med.or.jp/dl-med/people/info/symposium20240320/shiryo_2.pdf
在宅介護・医療のメリット
自宅で介護や医療サービスを受けるメリットは次のとおりです。
- 自由度の高い生活を送れる
- 家族と過ごせる時間が増える
- 患者に合わせた柔軟なケアができる
在宅によって期待できるメリットを詳しくみていきましょう。
自由度の高い生活を送れる
利用者は自宅でケアを受けられるため、施設に訪れる必要がなく、精神的な安堵感を得られます。
趣味の時間など、好きなときに好きなことができる自由度の高さは、高齢者向け施設や病院にはないメリットといえるでしょう。
介護の頻度も、介護施設では一定のサービスを必ず受けなければなりませんが、自宅であれば家族による自力介護の割合を増やすなどして、介護サービスの利用にかかるコストを抑えることもできます。
家族と過ごせる時間が増える
大切な家族と離れることなく、常にそばにいながら生活を続けられるので、QOL(生活の質)や満足度が向上します。
家族にとっても、病院や施設に入ったままいつ戻れるかわからないという不安がなく、大切な方の老後に寄り添えるという安堵感を得られます。
患者に合わせた柔軟なケアが出来る
臨機応変に柔軟なケアを組み立てられる点も、在宅介護・在宅医療の利点です。
一例として、継続的な医学的管理が必要な方には訪問診療を提供します。その時点で介護は必須ではなくても、リハビリテーションが必要になったときはデイケア(通所リハビリテーション)を利用し、機能の回復を目指すといった組み合わせが考えられます。
同じ高齢者でも必要とするサービスはそれぞれ異なるため、柔軟に対応できる在宅介護や在宅医療サービスが重要視されています。
在宅介護・医療のデメリット
在宅介護・医療には、「家族の負担が大きくなる」「緊急時の対応が施設に劣る」といった課題があります。
家族の負担が大きくなる
在宅介護では、家族が24時間365日高齢者の世話をしなければならない状況が生じます。
トイレや入浴、階段の昇降、その他の見守りをすべて家族だけで行う必要があり、休む時間を確保するのが難しく、負担が増大します。
さらに、介護に追われることで外出の機会が減少し、仕事や家事に割ける時間や心理的余裕が失われる点も課題といえます。
緊急時の対応が施設に劣る
在宅での介護では、医療設備や医薬品が整っていない、専門の医療スタッフが常駐していないといった理由から、突然のトラブルに対応できない場合があります。
その時々に応じた対応が可能な施設とは異なり、在宅介護では医療知識が乏しい方が介護を担当するケースが多く、緊急時に適切な対応が遅れる場合があります。
在宅介護・医療を支えるサービスと制度
次に、在宅介護・医療を支えるサービスと制度について説明します。
- 介護予防サービス
- 介護サービス
- 地域密着型サービス
- その他のサポート
【介護予防サービス】
介護予防サービスは、要支援1の方が利用可能な予防を目的としたサービスです。
「介護予防訪問看護」「介護予防訪問入浴介護」「介護予防居宅療養管理指導」「介護予防訪問リハビリテーション」といった複数のサービスを利用者に応じて組み合わせます。
要支援2の方は、「介護予防通所リハビリテーション(デイケア)」や「介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)」も利用できます。
【介護サービス】
介護サービスは、要介護1に認定された方を対象とした支援サービスです。
「訪問介護(ホームヘルプサービス)」「訪問入浴介護」「訪問リハビリテーション」のように、介護を受けながら生活を続けます。医療機関や訪問看護ステーションから医療従事者が訪問する「訪問看護」も要介護1の方が利用可能です。
【地域密着型サービス】
地域密着型サービスは、各地域の特性に合わせて市町村が事業者を指定または監督して提供するサービスです。
2006年4月の介護保険制度改正によって創設され、各地域に居住する方を対象とした小規模なサービスです。地域が限定されるため、利用者のニーズに細かく応えられる点で注目されています。
このサービスでは、夜間にホームヘルパーが巡回する「夜間対応型訪問介護」や「認知症対応型通所介護」といったサービスが提供されています。
【その他のサポート】
要支援・要介護認定を受けた方は、福祉用具の貸与や購入費、住宅改修費の支給といった追加の支援を利用できます。認定を受け、さらにケアマネジャーが策定するケアプランが必要です。
貸与される福祉用具には車椅子、特殊寝台、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器などがあります。例外的に、腰掛便座や簡易浴槽、入浴補助用具も購入可能です。
施設から在宅への移行を検討する際のポイント
施設から在宅への移行を検討する際には、必要なサービスやサポートが受けられるかどうかを確認する必要があります。
利用者が訪問介護や訪問診療の対象外である場合、在宅での看護や介護を受けることが難しくなります。事業者と自宅との距離や利用者の人数により、サービスの提供が難しい場合もあります。
在宅移行を進めるためには、主治医やケアマネジャー、看護職員といった職種がチームで関与することが求められます。そのため、ソーシャルワーカーや地域連携室といった専門窓口へ相談することが重要です。(※)
施設から在宅へ移行が進む理由は?
今回は、施設から在宅介護・在宅医療への移行が進む理由と、在宅のメリット・デメリットについて紹介しました。
高齢化社会が進展する中で、住み慣れた場所で生活を続けることへの関心が高まっています。訪問診療のように医療従事者が自宅を訪問するサービスは、高齢者が医療を受ける際の障壁を低くし、生活の質(QQL)の向上に寄与します。
在宅介護や在宅医療は自宅での生活を支援するサービスであり、今後、全国へさらに普及し、サービスがより充実すると見込まれています。施設から在宅への移行を検討している方は、一度専門家に相談し、具体的な手続きを確認してみると良いでしょう。
市川市・浦安市で訪問診療の受診をお考えの方は、
南行徳の面野医院 (訪問診療専用番号 047-321-4600)へご相談ください。