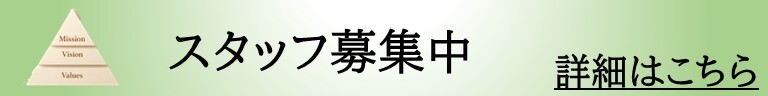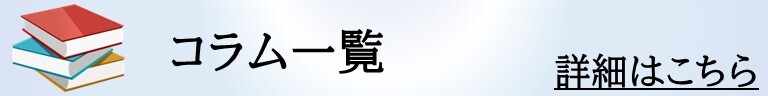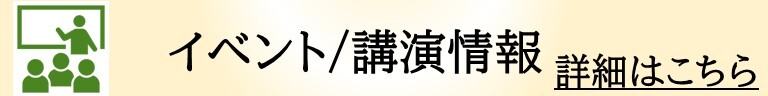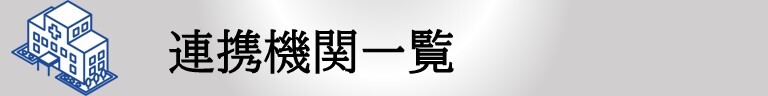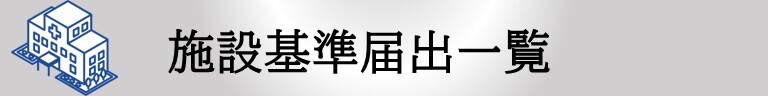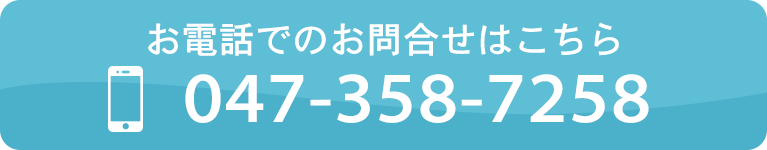在宅医療が普及しない理由とは?現状の課題と解決のための取り組み
日本における在宅医療は、高齢化社会の進行にともない需要が増えています。医療機関ではなく、自宅や施設で医療サービスが受けられる在宅医療は、高齢者や障害者、慢性疾患を抱える方などにとって貴重な選択肢です。
一方で、在宅医療はまだ十分に普及しているとはいえません。サービスの提供者不足や提供方法を整備する必要があり、利用希望者に対して十分にサービスが行き届いていない状況です。
この事では、在宅医療の現状と普及しない理由を中心に紹介しています。普及に役立つ取り組みや自治体ごとの取り組み事例も詳しくみていきましょう。

在宅医療の現状について
厚生労働省の発表では、後期高齢者の増加は2025年以降緩やかに推移すると推定されるものの、85歳以上の人口は2040年まで増加すると見込まれており、「医療」と「介護」の複合ニーズが増えると予測されています。(※)
また、死亡の場所については自宅や施設が増加傾向にあることも調査によって判明しました。自宅や介護施設は医療と介護を両立させ、高齢者が最期を迎える場としても機能するため、在宅医療へのニーズが高まっていくと考えられます。
※参照元:厚生労働省老健局老人保健課「在宅医療・介護連携推進事業の取組について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/001195365.pdf
在宅医療がなかなか普及しない理由
在宅医療が普及しない理由として、次の4点が挙げられます。
- 医療従事者の数が足りていないから
- サービスを提供する体制が整っていないから
- 家族向けの支援ができていないから
- 容体が急変した際の対応が難しいから
医療従事者の不足やサービスの提供・支援体制の不備、急変時の対応に関する問題が挙げられています。それぞれの理由を詳しくみていきましょう。
医療従事者の数が足りていないから
在宅医療が広く普及しない理由として、医療従事者の不足があります。高齢化社会の進行に伴い、対応できる医師や看護師の数が追いつかない人手不足の状態や、都市部と地方における医療従事者数の格差も一因となっています。
在宅医療ではさまざまな状況の患者さんを診察するため、専門的な知識やスキルが必要になります。複雑なケアに対する教育や研修を受けた医療従事者が不足していることも、在宅医療の普及を妨げる要因です。
サービスを提供する体制が整っていないから
医療スタッフの不足・医療機器を持ち込むための環境が整っていない・在宅医療を十分に提供できるだけの費用を確保できていないといった、サービスを提供する体制が整わない問題もみられます。
「患者さんが必要とする医療機器や設備と医療従事者を揃える」ことが、在宅医療を提供したくてもできないという現状につながっているのです。
設備やスタッフが揃っていても、病院・介護施設・薬局での連携がとれていないためにサービスの提供が妨げられることもあります。
家族向けの支援ができていないから
在宅医療は、医療従事者だけではなく患者さんのご家族からのサポートも不可欠です。
そのため、患者さんに適切な環境を用意するだけではなく、ご家族にも負担を軽減するための支援を行う必要があります。一例として、介護スキルの提供や福祉用具の貸し出し、精神的なサポートの提供が挙げられます。
ご家族への支援が十分に行われなければ、「家庭でケアするのは難しい」という判断になり、在宅医療の普及を妨げてしまう可能性があります。
容体が急変した際の対応が難しいから
病院であれば、患者さんの容体が急変したときにも担当医がすばやく対応します。専門的な処置が必要になっても、病院から病院への移動であればすぐに連携がとれるため、患者さんやそのご家族にとっても安心です。
一方、在宅ではご家族などが患者さんのケアにあたり、定期的な訪問診療のみの対応となってしまうため、緊急時の対応を希望される方は、在宅医療を選択しにくい可能性があります。
国が注力している在宅医療を普及させるための取り組み
ここからは、国が注力している在宅医療を普及させるための取り組みについてみていきましょう。
- 医療従事者の育成
- 在宅医療の基盤整備
- 災害や感染症への対策
- 在宅医療を提供する体制の強化
医療従事者の育成や災害・感染症対策といった項目について、詳しくみていきましょう。
医療従事者の育成
国では、在宅医療に特化した教育プログラムを提供するとしています。医療従事者が、在宅での診療を希望する患者さんに対して適切にサービスを提供できるように、知識と技術の習得を目標とする内容です。
実際の在宅医療現場を想定し、研修も強化するとしています。知識だけにとどまらず、実践的な場を提供し、より在宅医療を身近なスキルにしてもらう取り組みです。
医療従事者の育成とともに、教育にあたる専門家の支援も行っています。在宅医療に携わった経験のある人材を育成し、教育の機会を提供しています。
在宅医療の基盤整備
在宅医療の基盤整備として推奨・推進されている内容は次のとおりです。
- 医療設備の充実
- 医療従事者の育成
- 地域医療の充実・連携
- ITの導入と活用
- 支援制度の整備
在宅医療を十分に提供するための設備機器の整備や、医療サービスを提供する人材の育成、さらに地域医療として病院(診療所)・介護施設・市町村の役所や役場・福祉事業所などが連携する地域医療の整備が進められています。
作業の効率化や人手不足に対応するため、電子カルテやシステムの導入(IT化)も推奨されています。導入状況は個々で異なりますが、在宅医療をスムーズに行えるようにするために必要な項目です。
患者さんとそのご家族への支援制度として、医療費助成や介護サービスの提供といった支援体制の見直しや提供も課題のひとつです。
災害や感染症への対策
近年、地震や台風などの災害や世界的な感染症が発生・拡大し、従来の福祉サービスが機能しづらくなるというケースが報告されています。
国では、患者さんが災害や感染症の状況下にあっても適切な医療サービスが受けられるように、災害・感染症への対策にも力を入れようとしています。
厚生労働省では複数回の検討会を開き、令和4年にはかかりつけ医・患者さんとそのご家族・市町村や関係団体といった各所の連携体制を構築する必要があることを確認しました。(※)
※厚生労働省「総論16:災害時における在宅医療」
https://www.mhlw.go.jp/content/10802000/001086100.pdf
在宅医療を提供する体制の強化
国では、団塊の世代が75歳以上を迎える2025年をめどに、重度の要介護状態となっても自宅や施設などで暮らしを続けられるよう、医療・介護・住まい・生活支援・予防を包括的に確保できるよう、「地域包括ケアシステム」の構築を目指すとしています。
認知症を抱える高齢者の増加も見込まれるため、保険者である自治体ごとに地域の特性を活かし、自主性や主体性に基づいて体制を作り上げていく必要があるとしています。(※)
自治体ごとに注力している在宅医療を普及させるための取り組み
ここからは、自治体ごとに在宅医療を普及させるための取り組みをみていきましょう。
大分県佐伯市
大分県佐伯市では、医療と介護が一体となり支援体制を構築するために、関係機関と連携して在宅医療・介護の連携推進事業を進めてきました。
2024年11月17日には、佐伯市内において在宅医療の普及啓発を目的とした「さいき在宅医療介護推進フォーラム2024」を開催。市民が直接参加し、講演会や実施報告を通じて情報を取り入れ、福祉用具の展示やリハビリテーションへの理解を深めるための展示が行われています。
※参照元:佐伯市「「さいき在宅医療介護推進フォーラム2024」を開催します!」
https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0038776/index.html
神奈川県
神奈川県では、第8次県保健医療計画への位置づけとして、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」および「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」の見直しを行いました。
国の指針に基づき、神奈川県では在宅医療・介護連携推進事業の実施主体である市町村を、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」に位置づけ、県内の各医師会から推薦された「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」を指定しました。
「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」では、在宅医療の現場で研修を受ける機会などの確保に努め、災害時にも適切な医療を提供する計画の策定や、地域包括支援センターのような機関とも協働し、障害福祉サービスや介護といった、患者さんとそのご家族の負担を軽減できるサービスを適切に紹介する旨が定められています。(※)
※参照元:神奈川県「「在宅医療に必要な連携を担う拠点」及び「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」について」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6z/renkeikyotensekkyokuteki.html
在宅医療の普及に向けた取り組みをチェック
今回は、在宅医療の現状と普及が進まない理由、国や都道府県の取り組みについて紹介しました。
在宅医療は、通院が難しく医療を必要とする人々の一助となり、患者さんのご家族にとっても心強い医療サービスです。在宅医療を普及させるためのさまざまな取り組みによって、医療従事者の活躍の場も広がり、地域医療の整備や医療機関だけに頼らない新しい医療体制の構築にもつながると期待されています。
医療設備・医療資源・医療スタッフの不足や地域差といった問題もありますが、今後さらに国と地方自治体が体制を整え、在宅医療の重要性が周知されていくと期待されています。
市川市・浦安市で訪問診療の受診をお考えの方は、
南行徳の面野医院 (訪問診療専用番号 047-321-4600)へご相談ください。