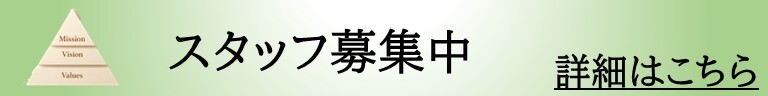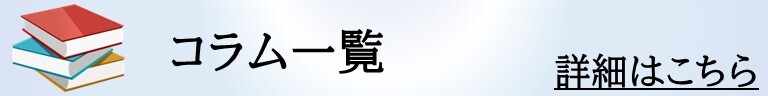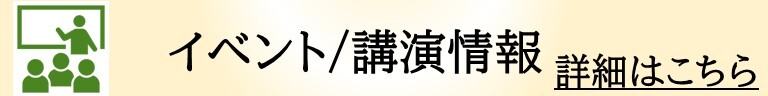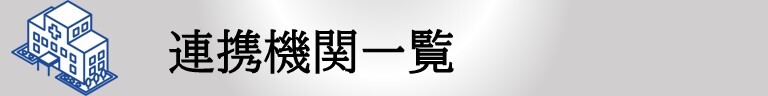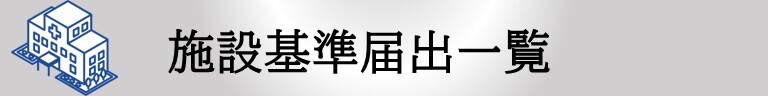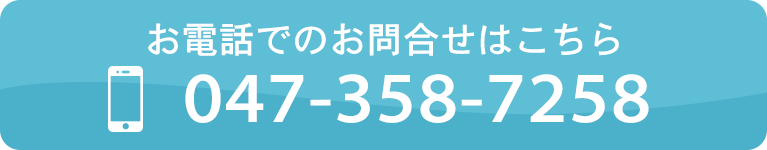在宅緩和ケアのメリットとデメリット・対象者と費用相場を紹介
在宅緩和ケアは、終末期にある患者さんとご家族が安心して過ごすための支援です。
病院で行われる医療・看護ケアとは異なり、住み慣れた自宅という環境で支援が提供されるため、患者さん自身がリラックスした状態で日々を過ごすことができます。痛みや症状の緩和以外にも、精神的なサポートやご家族の負担軽減といったサポートが提供されます。
この記事では、在宅緩和ケアの内容や対象となる方、メリット・デメリットについて紹介します。在宅で受けられる医療サービスを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
在宅緩和ケアとは
在宅緩和ケアとは、病気を抱える患者とその家族に対して、心身の苦痛を和らげるための医療処置・ケアを指す在宅医療の一種です。
主治医と訪問看護師、療法士や薬剤師などがチームを組み、患者さんの居宅に訪問してサービスを提供します。ケアマネジャーのように福祉に携わる専門職が連携するケースもあります。
在宅のまま医師や看護師からの診療が受けられるため、身体上の理由により通院や入院ができない方も住み慣れた場所で生活を送りながら、意思を尊重したうえで医療を受けることが可能です。
在宅医療では、決められたスケジュールに基づき患者の居宅へ訪問します。24時間365日医療サービスが受けられるわけではなく、普段のケアは患者さんのご家族が担当します。
在宅緩和ケアの対象となる方
在宅緩和ケアの対象となる方は、緩和ケアを必要とする次のような方です。
- 高齢者
- 末期癌の方
- 進行性の神経変性疾患の方
- 末期の慢性疾患の方
高齢者については、緩和ケアが望ましいと主治医から診断を受けている方や、老衰を控えた方が該当します。末期癌や末期の慢性疾患のように、何らかの疾患が末期の状態にある方も緩和ケアの対象です。
パーキンソン病やALS(筋萎縮性側索硬化症)などの神経変性疾患を抱える方も、在宅のまま緩和ケアが利用できます。
在宅緩和ケアを利用するメリット
在宅緩和ケアを利用すると、通院の負担を減らし自分らしい生活が続けられます。病院や施設に入らず、住み慣れた場所でケアを受けられるため、心理的な安心感があります。
思いどおりに体が動かせない、外出が難しいような患者さんも、移動に伴う負担がなく、自宅にいながら苦痛を緩和できるため、高い満足度と生活の質の向上が期待できます。
ここからは、緩和ケアを在宅で利用するメリットをみていきましょう。
通院の負担を減らせる
在宅医療のメリットは、自宅で過ごせるという自由度の高さと、通院にかかる負担の軽減です。
医師や訪問看護師、作業療法士などが自宅に訪問して必要なケアを行うため、通院にかかる身体的な負担と時間を軽減できることもメリットです。家族による送迎も不要になり、仕事やほかのスケジュールとの調整がしやすくなります。
生活の質を維持することができる
在宅緩和ケアは患者さんにとって安心感があります。病院や施設では一日のスケジュールが決められていますが、自宅であれば何をして過ごすかは自由です。
時間管理が厳しく、第三者の存在が気になる環境ではなく、リラックスできる自宅という空間を活用することができます。ケアを受けていないあいだは好きなように過ごしながら、一日の時間を思い思いに過ごすことができます。
医療処置は病院ほどの高度な設備が用意できないため基本的な内容にとどまりますが、病院より劣るわけではありません。病院で使う薬と同じものが在宅緩和ケアでも使われるため、ケアの質が高いことも特徴といえるでしょう。
在宅緩和ケアを利用するデメリット
在宅緩和ケアは自宅などで実施する医療サービスを指し、設備の整った医療機関とは異なるデメリットがあります。
- 家族の負担が増える
- 医師や看護師が迅速に対応できない可能性がある
- 最先端の治療は受けられない
- 看取りに対する知識と覚悟が必要
緩和ケアは患者さんのQOL(Quality of Life)を向上させるためのケアですが、家族の負担や迅速な対応が難しいデメリットがあります。看取りへの覚悟が必要なこと、最先端の治療に対応できない点にも注意が必要です。
4つのデメリットについて確認していきましょう。
家族の負担が増える
在宅緩和ケアを受けるために、ご家族が患者さんの身の回りを整えたり介助を行ったりするケースがあります。そのような役割が発生すると、ご家族の負担が増える可能性があります。
提供されるケアの内容にもよりますが、患者さんやご家族の意向、生活状況によっては負担が大きくなるため、事前にかかりつけの医師や専門家と話し合っておくことが大切です。
医師や看護師が迅速に対応できない可能性がある
医師や看護師は、病院のように24時間そばにいるわけではありません。いつでも往診できるように24時間体制で在宅医療を提供している事業者もありますが、すべての事業者が対応しているとは限らないため、基本的にスケジュールに合わせた対応となります。
病院では医療スタッフが常勤し、迅速に情報共有と対処を行うため、不安はありません。しかし、在宅緩和ケアでは医療スタッフが常に常勤しているわけではないため、対応に時間がかかるケースがあります。
訪問診療を行っている事業者が少ない、訪問診療にあたるスタッフの人数が不足しているといった状況では、即座に患者さんのニーズに対応できない場合も考えられるでしょう。
最先端の治療は受けられない
在宅緩和ケアでは十分な医療処置を受けられない可能性があります。薬の投与量を1日のうちに複数回調整するケースや、複数の病気に罹患している方は、在宅ではなく入院などを検討しましょう。
最新の設備機器を使った高度な治療も、在宅緩和ケアの対象外となります。病状が進行し緊急的な処置が必要になったときは、在宅のままでは対応できないため、医療機関への入院を検討しなければなりません。
看取りに対する知識と覚悟が必要
在宅緩和ケアでは、「看取り」への理解も重要なポイントになります。患者さんご自身の心の状態に配慮しながら、患者さんを看取るご家族も在宅緩和ケアを理解し、協力的な姿勢で臨む必要があります。
自宅で最期を迎えるため、看取りを医療チームにすべて任せるのではなく、ご家族でも主体的に知識を得て覚悟をもたなければなりません。
在宅緩和ケアの費用相場
日本赤十字社が運営する日本赤十字医療センターでは、緩和ケア病棟の費用を次のように定めています(負担割合1〜10割の場合)。
【緩和ケア病棟の費用相場】
| 項目 | 1割 | 2割 | 3割 | 10割 |
|---|---|---|---|---|
| 入院料(30日以内) | 5,051円 | 10,100円 | 15,150円 | 50,510円 |
| (31〜60日) | 4,514円 | 9,030円 | 13,540円 | 45,140円 |
| (61日以上) | 3,350円 | 6,700円 | 10,050円 | 33,500円 |
| 食事代 | 460円/食 | 460円/食 | 460円/食 | 640円/食 |
| 差額ベッド代 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 |
在宅緩和ケアにかかる費用は、利用者の負担割合や入院日数、差額ベッド代などのオプションの有無によって異なります。緊急時の往診やその他の医療処置、検査を行うとそのつど加算があります。
※参照元:日本赤十字社医療センター「緩和ケア病棟に関する費用」
https://www.med.jrc.or.jp/Portals/0/images/hospital/clinic/department/kanwa/kanwa_care_hiyou.pdf
在宅緩和ケアのメリット・デメリットを確認しよう
今回は、在宅緩和ケアの概要や対象となる方、メリット・デメリットについて紹介しました。
在宅緩和ケアは、自宅で過ごしながら無理なくケアを受けたいというニーズを満たす在宅医療です。さまざまな事情で入院を検討できないときの選択肢であり、患者さんの意思で病院ではなく自宅でのケアを選ぶような場合にも適用されます。
利用にかかる費用や診療体制など、細かい条件は地方自治体や在宅緩和ケアを実施する事業者、患者さんの状況によって異なります。まずは担当のケアマネジャーや医療ソーシャルワーカー、在宅緩和ケアのコーディネーターなどの専門家へご相談ください。
市川市・浦安市で訪問診療の受診をお考えの方は、
南行徳の面野医院 (訪問診療専用番号 047-321-4600)へご相談ください。