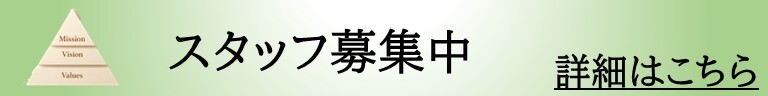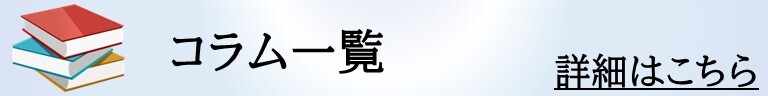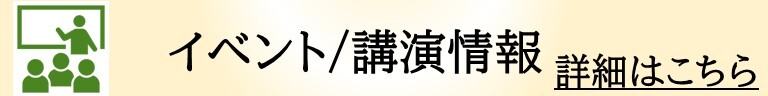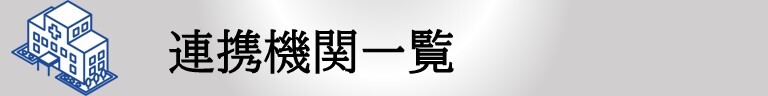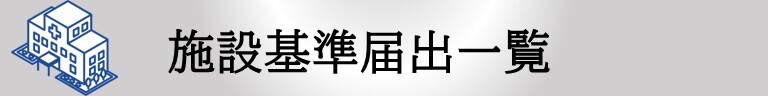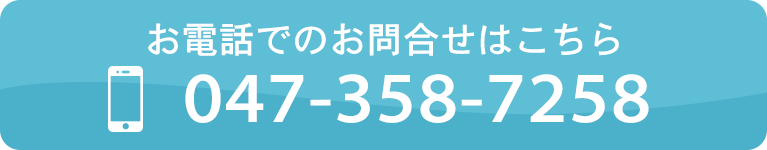訪問診療のメリットは?デメリットと共に解説
高齢化社会に入り、在宅で医療サービスを利用したい患者さんのために「訪問診療」の重要性が増しています。
訪問診療は、医師や看護師などの医療スタッフが患者さんの元に訪れ、看護や処置を行います。患者さんやそのご家族は通院する必要がなく、在宅でケアを受けられるため、負担が大幅に軽減されます。
患者さん一人ひとりに応じたケアを提供するため、医療の質の向上にもつながると期待されています。
この記事では、訪問診療の概要やメリットについて説明します。訪問診療の対象となる方々、デメリットについても取り上げていますので、ぜひご参考ください。

訪問診療とは?
訪問診療とは、医療上の必要性がある患者さんの元に医師や看護師が訪問し、診察・医療的処置・投薬・アドバイスを行う医療サービスです。
一般診療として、薬の処方や検査といった(超音波や心電図など一部の検査に限られる)項目を含み、検査結果の解説や治療の方向性の説明、リハビリテーション指導や専門病院・専門施設との連携も行います。
従来の医療サービスは、病院や診療所のような専門施設で提供されてきました。しかし、近年で高齢化が進む中、在宅で治療を受けることを希望する方が増加しています。すでに中等度以上の認知症を抱えており、施設から自力で病院へ通えない方なども少なくない状態です。
訪問診療は、そのような方々の健康を維持し、適切な治療を施すために役立てられています。移動の必要がないことで患者さんの負担が減り、リラックスした状態で診察を受けることができます。医師にとっても、患者さんの日常生活や生活環境を直接観察できるので、個別化されたケアが提供できるメリットがあります。
厚生労働省は検討会を開き、令和6年9月30日に「新たな地域医療構想」として、在宅医療の重要性を説明しています。資料では、入院した高齢者がベッドに寝た状態でいると筋力が低下することから、入院早期での離床とリハビリテーション、身体活動の増加を促し、在宅復帰を目指す必要性が取り上げられました。(※)
令和6年の時点で、在宅医療を提供する医療機関は横ばいとなっています。しかし、需要は2020年から40年にかけて、50%以上需要が増加すると予測されています。訪問看護の利用率も同様に、2025年以降後期高齢者の割合が7割を超えると見込まれることから、2040年以降に訪問診療の利用者数がピークを迎えると予測されています。
そこで、「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」として、住み慣れた地域で治し・支える医療を提案しています。都道府県ごとに協議と調整を行い、医療機関と高齢者施設など複数の機関が連携を強化し、実効性のある体制を整備するとしています。
※参照元:厚生労働省「新たな地域医療構想について」
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001309842.pdf
訪問診療を利用するメリット
訪問診療を利用するメリットは、次の4点です。
- 住み慣れた自宅で治療を受けられる
- 通院の負担を軽減できる
- 24時間365日対応してもらえる場合もある
- ワンストップで医師に相談できる
訪問診療は患者さんとご家族の負担を軽減し、個々の状況に合わせた診療が行えるため、医療の質の向上が期待できるサービスです。
メリットについて詳しく説明します。
住み慣れた自宅で治療を受けられる
患者さんは自宅や施設でサポートを受けながら診察も受けることができます。病院への移動・受付・待ち時間にかかる身体的・心理的負担を避けられるというメリットがあります。
通院に不安やストレスを感じにくく、家族などの目の届く場所でケアを受けられる点もメリットと言える良さがあります。
施設に入居している方はスタッフがそばにいるため安心感があります。自宅であれば家族などと一緒に医師の説明やアドバイスを聞けるので、治療方針やアドバイスを聞き逃さず共有しやすくなることも訪問診療の長所です。
通院の負担を軽減できる
慢性疾患や機能障害、認知症・知的障害などさまざまな状況にある患者さんは、病院やクリニックに足を運ぶだけでも大きな負担になることがあります。
訪問診療は準備をして通院し、自宅に戻ってくるというプロセスが発生しないため、「通院だけで疲れてしまう」心配がありません。
体調が悪いときでも、訪問診療なら自宅で待機するだけで適切な診察や投薬が受けられます。
24時間365日対応してもらえる場合もある
訪問診療を提供する医療機関や事業者によっては、24時間365日の対応が可能な場合があります。
夜間や土日祝日、年末年始のように病院が開いていない時間帯は通常の医療サービスが受けられませんが、24時間365日対応の訪問診療はどのような場合でも医療サービスの利用が可能です。
医療機関や事業者によっては、平日に通常の訪問診療の日程を組み、緊急時のみ24時間365日対応のサービスとしているところもあります。
※対応可能な時間帯は、訪問診療を受ける前に必ず確認をとることをおすすめします。緊急時の対応を実施していない場合には、救急車を呼ぶといったケースが発生するためです。
ワンストップで医師に相談できる
訪問診療では、医師が患者さんの健康状態を確認し、診察や治療を一度に行います。このため、患者さんは異なる科目ごとに複数の病院を使い分けたり、日程を組み直して通院したりする必要がありません。
心配事や体調に関する相談をその場で医師に相談できるため、次の訪問診療に向けて新たな治療方針を決めたり、処置の内容を変更したりできます。生活習慣上の注意点についてアドバイスも受けられます。担当医が変わるたびに説明する必要がなく、ワンストップで治療が受けられます。
病院や診療所の診察では、医師は患者さんの生活環境を目で見ることができませんが、一方、訪問診療では普段の生活状況を見ることができ、ご家族からの意見も得られるので、治療方針を定めやすく改善点のアドバイスも患者さんごとに提供できます。
訪問診療を利用するデメリット
訪問診療を利用するデメリットも確認します。
- 家族に負担がかかる
- サポート体制を負担に感じる場合もある
- 最先端の医療は受けられない場合がある
- 緊急時に対応してもらえない可能性がある
患者さんをケアするという負担のほか、最先端の医療サービスにかかれない点もデメリットになります。
詳しくデメリットの内容をみていきましょう。
家族に負担がかかる
訪問診療には必ず看護師が常駐するわけではありません。看護師が伴うケースもありますが、医師のみが訪問するケースの場合、患者さんのサポートはご家族の役割となります。
患者さんへのケアは、体調や状況に合わせてご家族が行わなければなりません。仕事やその他の予定がある方にとって、訪問診療をこなすだけでも時間的・体力的に負担となるでしょう。
サポート体制を負担に感じる場合もある
訪問診療は、患者さんの状況に合わせて実施されます。医師と看護師が常に同伴しているわけではなく、看護師のみのケアや医師のみの訪問もあります。
患者さんとそのご家族は、サポート体制が整わないことを負担に感じるケースがあります。重度の認知症を抱えており、自力で移動や寝起きができない方については、看護師不在の場合に看護師に代わってご家族がサポートを行わなくてはなりません。
ご家族に医療・介護の知識や技術が不足し、適切なケアを提供できないケースもあります。訪問診療を担当する医療従事者からアドバイスが受けられず、ご家族がストレスにさらされるという事例です。
最先端の医療は受けられない場合がある
高度な医療設備や手術・投薬対応、機能訓練士による専門的なリハビリテーションは、いずれも在宅では難しいため、専用の病院や施設に移動して行います。
訪問診療では、定期検診とそれに付随する処置が行われます。専門的な治療が必要と判断されたときには、在宅での診療から病院や施設への入院・入所を検討することになります。
緊急時に対応してもらえない可能性がある
患者さんの急変時や災害の発生といった緊急的な状況では、訪問診療が対応できない場合があります。万が一の事態に備えて、訪問診療以外の手段も整えておく必要があるでしょう。
訪問診療は在宅のまま診察や治療が受けられる
今回は、訪問診療の概要とメリット・デメリットについて紹介しました。
訪問診療は、自力で通院できない患者さんを助け、医療や生活の質を向上させるサービスとして注目されています。国や地方自治体でも地域医療と在宅医療の重要性を認識し、さらに連携体制を整えるとしています。
病院のように医療従事者が身近にいる環境ではありませんが、住み慣れた自宅や施設で医療サービスが受けられる方法のため、今後さらに需要が増えていくと考えられています。
市川市・浦安市で訪問診療の受診をお考えの方は、
南行徳の面野医院 (訪問診療専用番号 047-321-4600)へご相談ください。