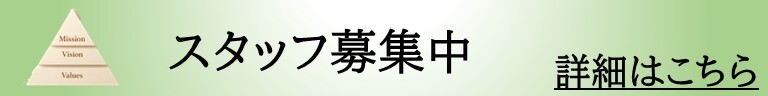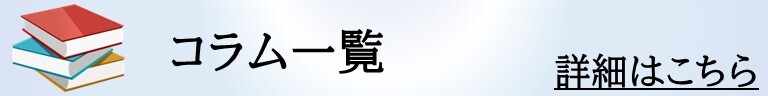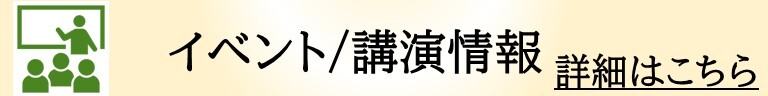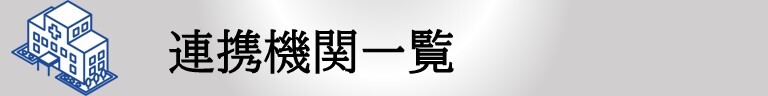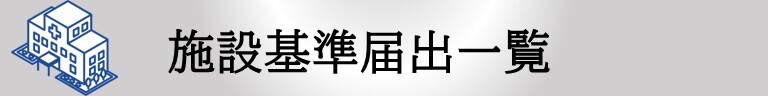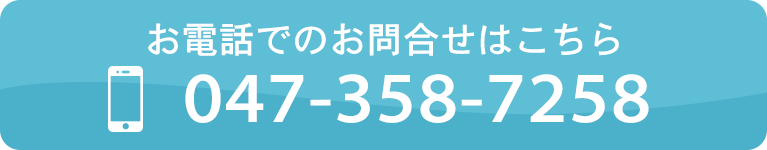認知症方を病院に連れて行く方法は?具体的な方法と注意点を解説
認知症は、近年の高齢化社会においてさらに増加が予測されている健康問題です。何らかの原因で脳機能が低下していき、記憶・判断・思考といった能力の低下を引き起こし、日常生活に支障をきたします。
この病気は早期発見と早期治療が重要です。重篤化する前に対処を始めれば、症状の進行を遅らせて患者さん自身が納得したうえで病気に向き合っていけるでしょう。
この記事では、認知症の早期発見・治療の重要性と診察を受けない場合のリスクについて紹介します。認知症の方を病院に連れていくためのポイントもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
認知症の早期発見・治療の重要性について
認知症の早期発見は、患者さん自身が正しく症状を理解し、適切なタイミングで治療を始めるために役立ちます。認知症は進行性のため、発見が遅れると治療が大幅に遅れ、その結果回復の可能性も限られてしまうためです。
認知症が中等度以上に進行すると、病状や治療計画を患者さんが理解しづらくなり、治療拒否や通院が難しくなるといったトラブルが考えられます。
しかし、患者さんがまだ正しく理解できるうちに認知症に向き合えば、家族などの介護者とも意思疎通を図りながら適切なサポートを受けられるようになります。
認知症の診断と治療法が改善されて新しい予防策や医薬品が開発されるなかで、これらの選択肢を早くから利用することが、長期的な健康維持に寄与するのです。
認知症の方が診察を受けないリスク
認知症の方が診察を受けないとき、次のようなリスクが考えられます。
- 症状悪化により日常生活が困難になる
- 受けられる医療・介護サービスの選択肢が減る
- 家族や介護者の負担が増加する可能性がある
症状悪化により日常生活が困難になる
診察を受けずにそのまま放置していると、自立した生活が困難になっていきます。たとえば、新しい情報を記憶する能力が低下してくると、経験した出来事や記憶した物事・会話の内容が思い出せなくなります。これにより、予定の決定・変更・約束を守るといった日常的な活動が難しくなってしまいます。
脳機能の低下により感情がうまくコントロールできなくなると、抑うつ、不安、イライラ、攻撃的な言動が増えるケースもあります。反対に、何もしたいと思えない「無関心」や「無動機(やる気の喪失)」が現れる場合もあり、コミュニケーションへの悪影響が問題になるでしょう。
受けられる医療・介護サービスの選択肢が減る
診断によって治療の方向性が決まりますが、すでに一定程度病状が進行していると、治療法やケアプランの選択肢が限られる可能性があります。
早期に診断を受けられれば、患者さんの年齢や症状の程度・内容に応じて対応策を検討できますが、その機会を逃すと適切な治療や介護サービスを受ける機会が減少します。
中等度以上〜重度では介護や入院といった手厚いケアが必要になることがあります。患者さん自身の判断力や理解力が低下するほど、受けられる医療・介護の選択肢は限られてしまうのです。
家族や介護者の負担が増加する可能性がある
認知症の症状が進んでくると、家族や介護者が行う日常生活のサポートが増加し、軽度の状態よりも負担が増えます。
早期発見・早期治療を行っていればケアの方法について介護者自身で学ぶ機会を得られますが、タイミングを逃すと認知症の方のサポートに回らなければならず、精神的なゆとりが失われ、適切なケアが難しくなります。
介護者自身が睡眠不足や仕事の効率低下といったトラブルに悩み、体調を崩すリスクが高まります。介護サービスや医療費がかかるようになると経済的な負担も増加します。結果として、いくつもの負担を抱えながらサポートを続けなくてはなりません。
認知症の方を病院に連れていく際の主な障害
認知症に罹患すると、症状の程度によっては通院や診察を拒否することがあります。
感情のコントロールがうまく行えなくなると、ただ拒否するだけではなく大声で叫んだり怒ったりといった、周囲にも影響する拒否反応が出る方もみられます。
「自分が病気だと認識していない」「医療機関や検査に対する恐怖や不安がある」という、2つの障害についてみていきましょう。
自分が病気だと認識していない
認知症の進行によって判断力・理解力が低下し、自分が病気だと自覚できないケースです。
患者さん自身は、すでに認知症という病気を正しく理解できない段階に至っており、それまでの健康な状態を記憶しているために、「まだ健康だから問題ない」と判断してしまいます。
医療機関や検査に対する恐怖や不安がある
医療機関での診察・検査・医療処置に恐怖心や不安を抱いているケースです。
大掛かりな治療は行われなくても、患者さんのイメージでは「何を言われるかわからない」「認知症ですと言い切られるのが怖い」「入院や高額な費用を請求されたくない」といったさまざまな不安があるため、受診をためらってしまう状態です。
認知症の方を病院に連れて行く方法
認知症の方を病院に連れて行くためには、いくつかのポイントがあります。
- 認知症患者の気持ちに寄り添う対応と提案をする
- 専門家の協力を得る
- 事前に準備をしておく
病院と聞くと、どんな診断を受けるのか不安に感じる方は少なくありません。そのため、患者さんの気持ちに寄り添いながら、対応と提案を行いましょう。
無理に病院へ連れて行こうとすると拒否や抵抗が出てきてしまうため、患者さんの状況や不安感に共感し、相手の立場に立ったコミュニケーションが重要です。
ここからは、病院を受診するための具体的な方法をみていきましょう。
認知症患者の気持ちに寄り添う対応と提案をする
認知症はさまざまな原因によって発症しますが、罹患する前は仕事や家庭に忙しくしていた方が多いため、認知症と診断されてからショックを受ける可能性があります。
落ち込みやすい患者さんの気持ちに寄り添いながら、「症状が軽いうちに適切な治療をすることで進行を遅らせる可能性がある」と説明してみてください。
「もの忘れが多くて迷惑だ」といった否定的な意見も避けてください。あくまでも患者さんの気持ちを優先し、「治るもの忘れもあるので対処できる」といった、ポジティブな声掛けと提案が大切です。
本人のことが心配なことを伝える
認知症になると、患者さん自身が不安を感じます。病気が進んだらどうしようと考え、そこからネガティブな気持ちが高まってしまいます。
そこで、身近な人が患者さんに寄り添いながら、相手の気持ちを汲んだ上で心配していると伝えましょう。どのような状況でも、「心配している」と伝えましょう。
病気が進むと患者さんもご家族も、みんなが大変な状況になると説明し、受診を説得してください。
嘘をついて無理やり受診させない
病院に連れて行きたいからといって、病院以外の場所を挙げて連れ出そうとするのは避けましょう。嘘をついて外出し、実際に到着した場所が病院だった場合、「嘘をつかれた」と、ネガティブに受け止めるかもしれません。
認知症は少しずつ進行するため、まだ理解や判断の力がある方は嘘をつかれたことに憤ったり不信感を募らせたりするおそれもあります。そのため、「心配している」「一緒に治していこう」といった、心からのメッセージを伝えるようにしてください。
健康診断を提案する
健康への意識が高い患者さんには、血圧を測ったり悩み事を先生に相談したりできる、と恐怖心を与えないような言い方に工夫してみてください。
病院には健康状態をチェックする医療器具があるため、患者さんにとって安心感があります。恐怖の対象ではなく、健康になれる場所として病院を提案するのもひとつの方法です。
もの忘れ外来を利用する
もの忘れ外来とは、認知症・もの忘れの専門家が診察する外来の病院です。精神科・脳神経内科などの専門医が診察し、MRIやCTによる精密な画像診断も受けられます。
なぜもの忘れが起きているのか、認知症の症状なのか知りたいという悩みがある方は、ぜひ受診を検討してみてはいかがでしょうか。
近所の方や友人の例を話してみる
近隣の友人や知人で認知症にかかり、病院を受診した例があれば、その事例を話してみましょう。
「怖い場所ではない」「他の人も利用している」と安心感を与えれば、「検査だけ受けてみよう」と前向きな気持ちを促せる可能性があります。
専門家の協力を得る
患者さんが信頼しているかかりつけ医(主治医)や訪問診療の利用、地域包括支援センターへの相談もひとつの方法です。
いずれも患者さんの状態やニーズによって利用できる手段です。その時々で必要なサービスを選択しましょう。
かかりつけ医に相談する
かかりつけ医は、認知症にかかわる専門医(脳神経内科医や精神科医患者など)に相談しましょう。
1回以上の診察履歴があれば、すでに患者さんとの信頼関係ができあがっており、患者さんが話を聞き入れてくれる可能性があります。
訪問診療を依頼する
訪問診療は、医師・看護師・療法士・薬剤師といった専門家がチーム医療として、利用者の居宅を訪問し医療サービスやケアを提供する方法です。
どうしても病院に行けない方には、定期的な診察と服薬管理のために訪問診療の利用を検討すると良いでしょう。
地域包括支援センターに相談する
地域包括支援センターとは、高齢者が自立した生活を続けられるように支援する機関です。
認知症の専門医と連携しながら介護保険サービスの相談にものっており、必要なサービスの提案や調整、その他の専門的なアドバイスが受けられます。
事前に準備をしておく
病院を受診する前には、必要書類を揃えて移動手段を準備しましょう。
準備によって患者さんがスムーズに医療機関にかかれるだけではなく、介護者もストレスを減らして通院をサポートできます。
必要書類(保険証、診察券など)の準備
保険証、マイナンバーカード、医療機関の診察券を準備します。服薬をしている方はおくすり手帳の提示も求められます。他院から新しい病院に移動したときは、前の病院から受け取った診断書を持参します。
移動手段(車、タクシー、訪問診療)を決めておく
移動手段として、自家用車・タクシー・公共交通機関を準備します。患者さんの健康状態に適した手段を選びましょう。
診察当日の注意点
診察当日は、患者さんが不安感から体調不良を起こす、あるいは感情が不安定になるおそれがあります。
スムーズに診察を受けてもらうために注意したい3つのポイントは次のとおりです。
- 本人の体調や気分を優先する
- 事前に簡単な食事や休憩を取り入れる
- 現在の症状や必要な支援を把握しておく
体調や気分が優れないときは、無理に通院を促す必要はありません。心身へのストレスを減らすために、通院前の休憩や食事の時間も大切にしましょう。
本人の体調や気分を優先する
診察は、認知症の方にとってストレスのかかる行動のひとつです。ご本人の体調や気分を優先し、状態の良いときをみて通院を促しましょう。
事前に簡単な食事や休憩を取り入れる
待ち時間が発生する医療機関では、空腹や睡眠不足が患者さんのストレスになってしまいます。事前にしっかりと眠れたかどうかを確認し、受診前に簡単な食事・休憩も取り入れてください。
現在の症状や必要な支援を把握しておく
認知症の方が症状を伝えられないときは、介護者の意思決定が重視されます。患者さんの現在の症状や、必要なサポートを把握しておきましょう。
病院に連れていくためのポイントや注意点を確認しよう
今回は、認知症の認知症の早期発見・治療の重要性について、病院に連れて行く方法や診察日当日の注意点などを紹介しました。
病院に無理やり連れて行ったり、不安を与えて治療を受けさせるといった方法は避け、ご家族や知人の方が患者さんと一緒に方向性を考えるといった、前向きな対応が効果的です。
認知症の早期発見・早期治療は、患者さんの生活の質を維持したり病気の進行を遅らせたりするために重要です。まずは早期に症状を認識し、患者さん自身でも適切に医療サービスを受けていくことが、将来的な負担軽減や適切な治療の選択につながります。
市川市・浦安市で訪問診療の受診をお考えの方は、
南行徳の面野医院 (訪問診療専用番号 047-321-4600)へご相談ください。