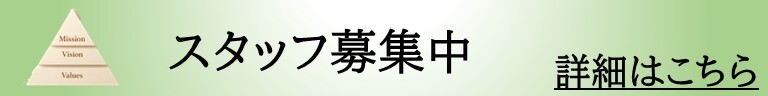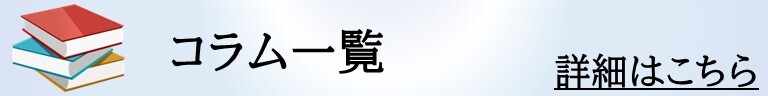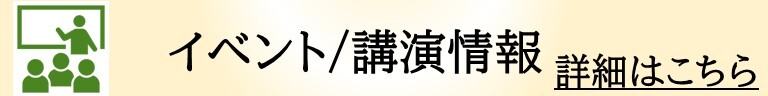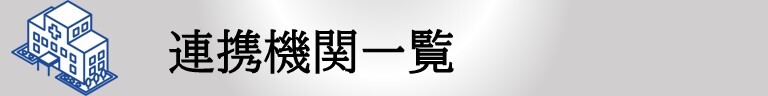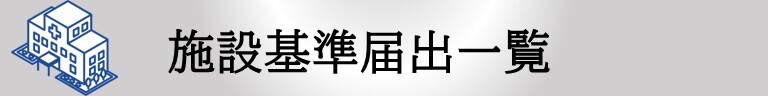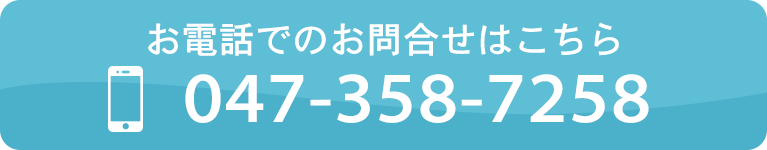認知症患者の通院付き添いで生じやすい課題と負担を軽減する方法
「認知症患者の通院には付き添いが必要?」「通院付き添いの負担を軽減したい」などと考えていませんか。どのように対応すれば良いのか分からず、困っている方も少なくありません。結論として、認知症患者さんの通院には付き添いが必要とされています。ここでは、その理由を紹介するとともに、認知症患者さんの通院付き添いで遭遇しやすい課題、課題の対処法を解説しています。認知症患者さんの通院でお困りの方にとって参考になる内容です。
認知症患者の通院に付き添う必要性
一般的に、認知症患者さんの通院には、付き添いが必要と考えられています。主な理由として以下の点があげられます。
移動が困難
認知症患者さんの通院には、さまざまなリスクが伴います。高齢者が多いため、徒歩で移動する場合は転倒すること、自転車や自動車で移動する場合は交通事故を起こすことが考えられます。タクシー、バス、電車を利用する場合も注意が必要です。足腰が弱っていたり、身体が不自由だったりすると、転倒などのトラブルを起こしやすいためです。
また、認知症患者さんの場合、記憶障害によって目的を忘れる、または見当識障害で現在地がわからなくなることがあります。見当識障害は、時間や場所などがわからなくなる認知症の中核症状です。認知症患者さんは、一人での移動が難しいと考えられます。
薬の服用の仕方を理解できない
病気で通院した際に、薬を処方されることがあります。その際に求められるのが、医師や薬剤師によるお薬の効果や副作用、服用方法などの説明を正確に理解することです。認知症患者さんは、服薬の必要性を理解できない場合や、服薬指導に最後まで集中できない場合が少なくありません(具体的な影響は、認知機能障害により異なります)。認知症患者さんの正しい服薬をサポートするため、通院に付き添ったほうが良いと考えられています。
訪問介護サービスを利用する
訪問介護サービスはホームヘルプサービスとも呼ばれるものであり、介護福祉士やホームヘルパーが自宅に赴いてさまざまなサービスを提供します。
例えば、入浴や排泄、食事の介助、洗濯、掃除、調理などが含まれます。また、通院時の外出サポートなども用意されているので、一人で通院するのが難しい場合は通院時の外出サポートを活用してみましょう。
診察内容を理解できない
認知症で理解力や判断力が低下すると、医師の説明を誤解することや理解できないことも考えられます。また、医師の説明を受け入れないこともあるでしょう。認知症患者さんが一人で通院すると、必要性が認められても治療や通院を継続できないことがあります。このようなトラブルを防ぐため、受診時には付き添いによるサポートが求められます。ただし、付き添う方が、認知症患者さんを管理することは勧められません。本人のプライドを傷つけてしまう恐れがあります。苦手なことを克服できるようサポートすることが大切です。
認知症患者の通院付き添いにおける課題
続いて、認知症患者さんの通院付き添いで遭遇しやすい課題を解説します。
病院が遠方だと1日がかりになってしまう
遠方の病院に通院していると、付き添いに1日かかることがあります。移動に時間がかかるうえ、一定の待ち時間も発生するためです。特に、複数の診療科を受診している場合や大規模な病院を受診している場合は、所要時間が長くなりやすいといえるでしょう。
通院に時間がかかると、付随する課題も発生しやすくなります。例えば、移動中に尿意や便意をもよおしトイレを急いで探さなければならない、通院で疲労がたまり体調を崩す可能性も考えられます。また、付き添う側の負担が重くなる点にも注意が必要です。
予定の調整が難しい
通院の頻度や付き添う側の環境によっては、予定の調整が難しくなることもあります。例えば、付き添う側が働いていて、通院の付き添いに1日かかると、その日は仕事を休まなければなりません。週に1回、週に2回などのペースで付き添いが発生すると、予定の調整が難しくなるでしょう。通院頻度、通院期間によっては、有給休暇を使い切ってしまうことも考えられます。仕事などで予定の調整が難しい場合は、適切な対策を講じる必要があります。
遠方に住んでいると頻繁に帰れない
ご家族が遠方にお住いの場合、付き添うために帰省しなければなりません。交通費がかかるうえ、一定期間の休みも必要になるでしょう。したがって、頻繁に帰省したり付き添ったりするのが難しい場合も多く見られます。また、認知症患者さんと接する機会が少ないため、普段の状況や症状の進行を把握しにくい傾向もあります。これらの点も、付き添う際に注意したいポイントです。
自分一人で抱え込んでしまう
サポート役のご家族が、頑張り過ぎてしまうことも認知症の付き添いで発生しやすい課題です。特に、1人で対応している方に多い課題といえるでしょう。育児、家事、仕事、介護などを並行して行うと、自分の時間を確保できなくなる場合があります。気がつくと、疲れ果てていることがあります。認知症患者さんの介護は、長期間に及ぶことが少なくありません。無理なく継続できる環境を整えることが重要です。
通院付き添いの負担を軽減する方法
認知症患者さんの通院付き添いに、負担を感じている方は以下の対策を検討するとよいでしょう。
家族を頼る
認知症患者さんを1人で支えると、負担が重くなってしまいます。通院の付き添いから日常生活の介助まで、1人で対応しなければならないためです。1人で頑張っている方は、他の家族を頼るとよいでしょう。家族全体で支える体制を構築することで、1人あたりの負担を軽減できます。例えば、通院の付き添いをローテーション制にすると、忙しい方でも予定を調整しやすくなるでしょう。家族全体で認知症患者さんの状態、状況を共有し、それぞれが主体的に参加できる環境をつくることが大切です。
ヘルパーを頼る
認知症患者さんが要介護認定(要介護1~5)を取得している場合は、介護保険サービスの通院等乗降介助を利用できる可能性があります。通院等乗降介助は、ヘルパー(訪問介護員など)が、車両への乗降やその前後の移動、通院先での移動や受診手続きなどを支援する介護保険サービスです。ただし、病院内での介助は原則として受けられません。診察への付き添いは基本的にできないため、注意が必要です。要介護認定を取得していて、通院等乗降介助を利用したい方は、担当ケアマネジャーに相談するとよいでしょう。要介護認定を受けたい方は、市町村の窓口や地域包括支援センターで相談できます。
訪問診療を活用する
通院の付き添いが難しい場合には、訪問診療の活用を検討することができます。訪問診療は、次のように定義されています。
在宅療養を行う患者であって、疾病・傷病のため通院が困難なものに対して定期的に訪問して診療を行うこと。 引用:内閣府 地方創生推進事務局「往診・訪問診療とは」 https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/150123siryou02_2.pdf
対象は、病気などで通院が難しい患者さんで、自宅などで療養を希望している方です。診療上の必要性が認められる場合には、往診を利用することも可能です。往診の定義は次の通りです。
医師が、予定外に、患家に赴き診療を行うこと。 引用:内閣府 地方創生推進事務局「往診・訪問診療とは」 https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/150123siryou02_2.pdf
認知症患者さんで通院が難しい方は、訪問診療の利用を検討するとよいでしょう
外部サービスを利用する
要介護認定を取得していない場合やプラスαのサービスを希望している場合は、介護保険の対象外となるサービスを活用する選択肢もあります。具体的なサービス内容はケースで異なりますが、診察室に同行する、ご家族に診察内容を説明するなど、手厚いサービスを提供していることがあります。ただし、介護保険を適用できないため、費用は原則として全額自己負担です。サービス提供事業者は、インターネット検索や地域包括支援センターなどで見つけられます。
認知症患者さんの通院付き添いは計画的に
ここでは、認知症患者さんの通院付き添いについて解説しました。移動が難しくなったり、判断力や理解力が低下したりするため、認知症患者さんは通院の付き添いが必要と考えられています。ただし、ご家族が1人で対応すると負担が重くなってしまいます。負担を軽減するため、家族全員で対応する体制をつくる、介護保険サービスを利用する、訪問診療を利用するなどの対策が必要です。認知症患者さんの通院付き添いは計画的に行いましょう。
市川市・浦安市で訪問診療の受診をお考えの方は、
南行徳の面野医院 (訪問診療専用番号 047-321-4600)へご相談ください。
📞047-321-4600からお電話でも受付中(診療時間内)
訪問診療についてのお問い合わせはこちら