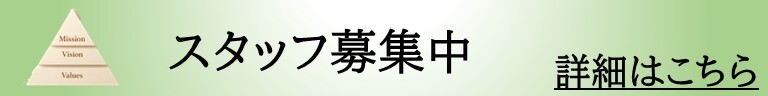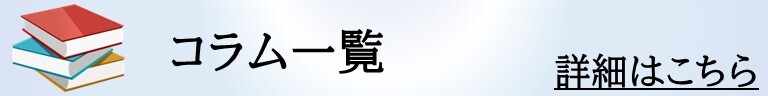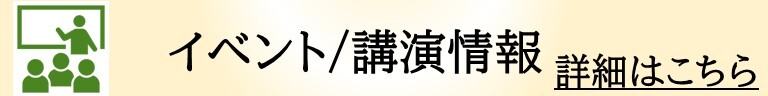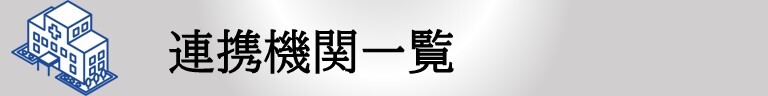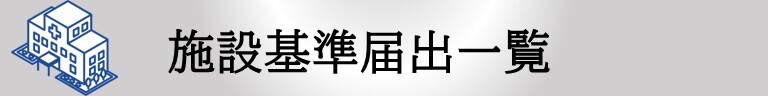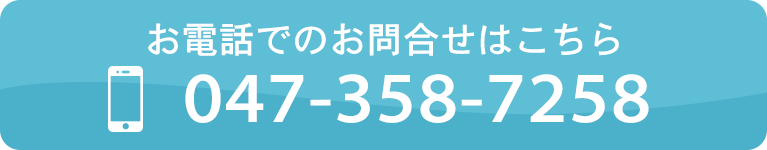動けない人を病院に連れて行くには?注意点を状況別に解説
急な発熱や嘔吐、その他の既往症・認知症といったトラブルが原因で動けなくなってしまうと、その人は自力で病院に行けなくなります。
大切な家族に万が一のことがあると、家族にとって心配が大きくなるものです。緊急事態でも慌てずに対処するためには、どのようなポイントに注意し、どの手順で行動すべきなのでしょうか。
この記事では、動けなくなった人を病院に連れていくときの緊急時対応について紹介します。
具体的な対応方法に加えて、非緊急時の移送手段や病院に連れていく際の注意点も取り上げています。ぜひ参考にしてください。
緊急時の対応について
突然の体調不良や既往症の悪化、転倒などのトラブルについては、次のポイントを押さえておきましょう。
- 状況を把握する
- 自身と周囲の安全を確認する
- 通報や声掛けを行う
- 家族などの関係者に連絡する
緊急事態が発生したときは、まず状況を把握しましょう。誰が、どこで、どのような状況に直面しているかを確認し、すぐに急病者とご自身の安全を確保してください。
たとえば、道路上で急病者が倒れるなどの危険な状況に遭遇したときは、可能なかぎり安全に対応できるように心掛けます。倒れた場所にもよりますが、安全が確保できるところへ移動させるなどの対応をとってから病院やご家族に連絡してください。
安全が確認できたら、119への通報、周囲への応援要請、声掛けを適切に行います。無理に行う必要はありませんが、救急車が必要な場合は速やかに要請してください。
家族などの関係者に連絡するケースは必須ではありませんが、状況によっては必要になることがあります(急病者自身から頼まれた場合など)。救急車が到着するまでに時間があるときは、状況をみて関係者へ連絡を行ってください。
救急車の利用基準
救急車の利用基準として、政府広報で提示されている条件は次のとおりです。(※)
- 緊急性の高い症状があるとき
- 一刻を争う状況のとき
- #7119で救急車を要請したとき
痙攣や昏睡といった緊急性が高い症状や、事故など一刻を争う状況が発生している場合には、救急車を要請する必要があります。
急な病気やケガについて救急車を呼ぶべきか判断が迷う場合には、『#7119(救急安心センター事業)』に相談できます。また、救急車が必要であると判断された場合には、すぐに救急車を要請してください。
※参照元:政府広報オンライン「もしものときの救急車の利用法 どんな場合に、どう呼べばいいの?」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201609/1.html#fourthSection非緊急時の移送手段
緊急性がない場合には、急病者を医療機関に移送してください。移送手段として選べる方法は次のとおりです。
- 介護タクシー
- 民間救急サービス
- 家族や友人の送迎
- 公共交通機関
自主的な送迎や公共交通機関の利用に加えて、タクシーや救急サービスを利用することも可能です。
介護タクシーを利用する
介護タクシー(福祉タクシー)は、移動をサポートするために設計された専用のタクシーサービスです。
ドライバーが介護の資格を保有している場合も多く、自力での移動が難しい方を介助して乗降させるといったサポートのほか、車椅子・ストレッチャーでの移動を支援します。
民間救急サービスを利用する
民間救急サービスとは、民間企業が提供する医療輸送サービスのことです。自治体の救急サービスとは異なり、消防局に認定を受けた搬送事業者が、患者の医療搬送を担います。
医療資格をもつスタッフが在籍し、公共の救急車と同様の医療機器・設備を搭載した救急車で現場に駆けつけます。
長距離移動に対応できる場合もありますが、サービスの内容や対応範囲は事業者ごとに異なります。詳しくはお住まいのエリアの民間救急サービスにお問い合わせください。
家族や友人が送迎する
緊急性が低い移動の場合は、家族や友人による送迎を検討することができます。
自家用車やレンタカー、その他の手段で送迎を行う方法で、介護タクシーや民間救急サービスよりも心理的なハードルが低い点がメリットです。
公共交通機関を利用する
すぐに医療機関を受診する必要性がなければ、公共交通機関の利用も検討できます。バスや電車、その他の移動手段を使えば、介護タクシーなどのサービスよりも安く目的地に到着できるでしょう。
ただし、自力での移動が難しい場合や、公共交通機関の利用中に体調が悪化する可能性がある場合は、無理をせずタクシーなどの方法で移動してください。
訪問診療の利用も検討する
訪問診療は、医療従事者が患者(利用者)の居宅を訪問して診察や検査を行う医療サービスです。
医療機関への通院が難しいときは、訪問診療に切り替えることで継続的な診察が受けられます。訪問診療では血液検査、尿道カテーテルの設置、看取りなど、多様な医療行為に対応しており、専門的な治療や手術が必要な場合は迅速に入院対応へ切り替えることができます。
訪問診療の対象となる方
訪問治療の対象者は、病気や認知症・障害などで通院できず、医師から訪問治療が必要と認められた方です。
回復が見込まれる病気や、一時的に施設に滞在している方、また訪問診療を提供している医療機関から遠距離にある場合は対象外となります。
原則として月に2回まで訪問が可能であり、中長期的なスケジュールに基づいて診療が継続されるため、「1回だけ来てほしい」「スケジュール通りに対応できない」といった場合も対象外になります。
訪問診療を検討する方は、訪問診療の仕組みを理解したうえで診療所や医療機関に相談し、訪問診療が受けられるかを確認してください。
訪問診療のメリット
訪問診療は、通院が困難な方が住み慣れた場所で医療サービスを受けられる仕組みです。
医師や看護師、薬剤師、療法士などが連携してチーム医療を提供するため、複数の医療機関を掛け持ちすることなく、移動の手間と負担を省いて健康管理を続けられます。医療の専門家が定期的に訪れるため、既往症の悪化や異常を早期発見できます。
自宅などの住み慣れた環境で診察を受けることは、医療機関で受診する場合と比較して心理的負担が軽減され、ストレスを軽減した状態が維持できます。家族が介護者として通院に付き添う必要がなくなり、時間や労力の負担が軽減されます。
病院に連れていく際の注意点
急患の方を病院に連れていくときは、「緊急連絡先を確認しておく」「必要な書類・持ち物を確認」という2点に注意が必要です。
それぞれのポイントを詳しくみていきましょう
緊急連絡先を確認しておく
緊急連絡先とは、急患が救急車で搬送されるなどの緊急事態を速やかに知らせるための連絡先です。
入院が必要になったとき、身元を保証する家族や知人が求められるため、緊急連絡先を確認しなければなりません。指定する相手は家族や親戚が多くみられますが、友人・知人・パートナーといった第三者でも問題ありません。
ただし、緊急連絡先が患者自身と疎遠、面識がほとんどないようなケースでは、連絡先として不十分になる可能性があります。すぐに連絡がとれて、急患の方の状況を把握できる方を指定する必要があります。
緊急連絡先として確認すべき事項は以下の通りです。
- 名前
- 続柄(例:父、母、友人など)
- 連絡先・電話番号
- 住所
連絡先の方の名前と続柄、連絡先の電話番号や住所は最低限チェックしておきましょう。
必要な書類・持ち物を確認
次に、病院を利用するための書類や持ち物を確認します。かかりつけ病院の診察券、保険証(またはマイナンバーカード)に加えて、診断書などの必要書類があれば持参してください。
入院の可能性がある場合は、普段服用している薬、着替え、寝具、シャンプーなどの持ち物も準備してください。
紹介状(診療情報提供書)が必要な医療機関では、主治医からの紹介状が必要です。入院手続きには印鑑が必要であり、薬の処方にはお薬手帳が求められるため、持ち物が揃っているか確認しておきましょう。
動けない人を病院に連れて行くには?
この記事では、動けなくなった人を病院に連れて行く際の対応方法や緊急時の対処方法について解説しました。
動けなくなった人を見かけた場合は、緊急性の度合いに応じて対処方法を判断し、生命に関わるような状態の場合は速やかに救急車を要請してください。一方で、問題なく会話ができる場合は緊急性が低い可能性があるため、#7119などの専門機関に相談することを検討してください。
障害や慢性疾患が原因で継続的な通院が困難な場合は、訪問診療を検討することが推奨されます。利用者である患者さんの状況から、どの方法が適しているかを考えたうえで対応しましょう。
市川市・浦安市で訪問診療の受診をお考えの方は、
南行徳の面野医院 (訪問診療専用番号 047-321-4600)へご相談ください。