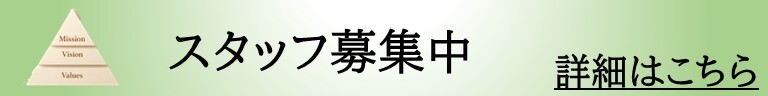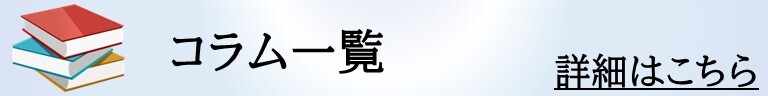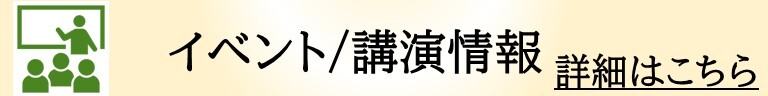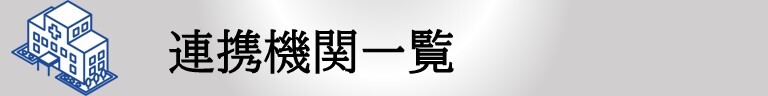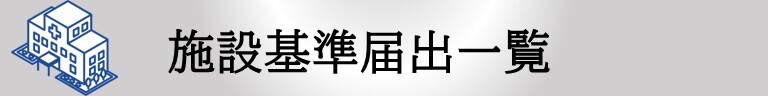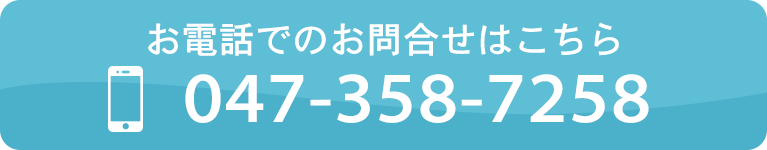末期ガンの家族を在宅看取りするときに後悔しないためのポイント
悪性新生物と呼ばれる「ガン(癌)」は、細胞が体の各所で異常に増殖していく病気です。
加齢やストレス、喫煙や食生活などさまざまな要因によって特定部位の遺伝子が傷つけられると、そこにガンが発生します。通常、遺伝子についた傷は自然に修復されますが、修復作業がうまくいかずに遺伝情報が変更されるとガンが発生する仕組みです。
ガンは初期から末期までいくつかの段階を経て進行します。この記事では、末期ガンの特徴や終末期について詳しく取り上げています。末期ガンにおける訪問介護の役割についても紹介していますので、後悔しないためのポイントを押さえておきましょう。
末期ガンは急性の病気ではなく、ステージ0から4までの5段階を順に進行します。ステージごとの特徴は次のとおりです。
| ステージ | 特徴 |
|---|---|
| ステージ0 | ガンが粘膜や上皮細胞内に留まっている リンパ節への転移はない |
| ステージ1 | ガンが少し広がり、筋肉層で留まっている リンパ節への転移はない |
| ステージ2 | ガンがさらに広がり、筋肉層を超えて浸潤 ややリンパ節への転移がみられる |
| ステージ3 | ガンがさらに浸潤し、リンパ節への転移がある |
| ステージ4 | ガンがはじめにできた場所から他の臓器などに転移している |
ガンのステージは、TNMと呼ばれる分類によって5つの段階に分けられています。Tは発生したガンの広がり具合や深達度、Nはガン細胞のリンパ節への転移や広がりの程度、Mは原発から離れた臓器への転移を示します。(※1)
上記のステージを検査などから確認し、複数の医師による見解をすり合わせて終末期を判断します。
末期ガンは5つのステージのうち、ステージ4に相当する状態です。ただし、ステージ4に至ったすぐに末期と診断されるわけではありません。
末期とは、治療法がほとんど存在せず根治も難しい状況です。医師は患者さんの状態を多角的に診断し、末期かどうかを判断しています。(※2)
※1参照元:国立がん研究センター がん情報サービス用語集「TNM分類」
https://ganjoho.jp/public/qa_links/dictionary/dic01/modal/TNM_bunrui.html
※2参照元:公益財団法人長寿科学振興財団 健康長寿ネット「がん(がん末期)」
終末期を過ごす主な場所
厚生労働省によれば、終末期とは次の3つの条件を満たす場合です。(※)
- 医師が客観的な情報をもとにして回復が期待できないと判断すること
- 意識や判断力を失った場合を除き、患者・家族・医師・看護師などの関係者が納得すること
- 患者・家族・医師・看護師などの関係者が死を予測して対応を考えること
治療によって回復が期待できないと医師が判断し、その後医療従事者や家族、患者さん自身が状況を把握します。患者さんの意思が明確にされているか、明確な場合は文書化されているかといったポイントを確認し、終末期医療の方針を決定します。
患者さんの意思によって、終末期を過ごす場所は「自宅」「介護施設」「病院」の3ヶ所に分けられます。終末期をどこで過ごすのかについては、医療従事者と患者さん、患者さんの家族が話し合って決めることが大切です。
※参照元:厚生労働省「終末期医療に関するガイドライン~よりよい終末期を迎えるために~」
自宅
厚生労働省によると、在宅医療を受ける人の死亡場所のうち自宅で亡くなる人の割合は1951年から2014年までの約60年で82.5%から12.8%まで減少しました。(※)
自宅は多くの場合患者さん自身への癒しとなります。病院や介護施設よりも住み慣れた環境であり、家族やペットなどに囲まれて安心感のある終末期を迎えられます。
一方で、適切な医療ケアや看護、症状緩和が行われなければ不安感が伴うこともあります。同居者がいない、または同居者に医療従事者がいないような環境では介護や見守りが不十分になる懸念もあり、患者さんの希望だけではなく症状に応じた環境を選ぶことが大切です。
※参照元:厚生労働省「看取りを念頭に置いた在宅医療の実際」
介護施設
介護施設では医師や看護師が定期的に訪問診療を行い、介護と医療の連携体制を整えています。施設に常勤するケースもあります。さらに高齢化社会への対応策として、ガンにかかった方の最期をサポートする施設が増えています。(※1)
有料老人ホームや特別養護老人ホームなど、認知症や既往症による介護度の高い入所者を受け入れている施設では、医療従事者と介護職員が協働して看取りケアにあたっています。
介護施設で終末期を迎える場合は、医療行為の必要性や優先度を考慮し、看護師の常勤や医療機関が併設されているか(または24時間連動しているか)、急変にすぐ対応してもらえるかといった点を中心に検討しましょう。(※2)
※1:「看取り」は施設で行われるケアの種類です。医療現場における、痛みを抑えるための処置「ターミナルケア」と区別されています。
※2参照元:公益社団法人全国有料老人ホーム協会「~豆知識~有料老人ホームの看取りケア」
病院
終末期に対応している病院は、「緩和ケア病棟」「療養型病院」「介護医療院」などが該当します。
療養型病院や緩和ケア病棟は、ガン治療における痛みや不具合を和らげる緩和ケアを中心に提供している病棟です。介護医療院は、患者さんへの「長期療養のための医療」と「日常生活上の介護・世話」を一体的に提供する施設です。(※)
終末期の生活を送りながら、必要な医学的処置や管理、介護なども受けられる施設で、症状が重くなっても最期まで必要なケアやサービスが受けられます。
※参照元:厚生労働省「介護医療院について」
末期ガンにおける訪問介護の役割
末期ガンの患者さんは、医療機関以外では自宅や介護施設での居宅サービスとして訪問介護を利用しています。
居宅サービスとしての訪問介護の役割は次の3つです。
- 身体のサポートをする
- ご家族の相談を受ける
- 関係各所と連絡をとる
ここからは、3つの役割について詳しくみていきましょう。
身体のサポートをする
自宅や施設への訪問介護は、身体的な不自由や不具合を抱える方へのサポートの役割を果たします。
患者さんは住み慣れた場所で通常どおり過ごしながら、介助や移乗といった必要なサポートを受けることができるため、安心感があります。患者さんにとっては、普段どおりの生活の中で支援を受けられる点が大きなメリットです。
ご家族の相談を受ける
訪問介護では、患者さんやケアを行う家族から相談を受けて、対処法やその他のアドバイスを行っています。
訪問介護では介護サービスを中心に提供していますが、精神的なケアとして患者さんの恐怖心や不安をヒアリングし、当事者に寄り添うことで安心感を与えます。場合によっては医療機関とも連携し、適切な医療に繋げます。
自宅で介護を行うご家族が何らかの心配事やストレスを感じているときは、その思いにも寄り添います。ただし、訪問介護員(ホームヘルパー)は相談員ではないため、専門的なアドバイスは関係各所への連絡が必要です。
関係各所と連絡をとる
専門的な見解が必要な相談については、ケアマネジャー・民生委員・居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・社会福祉協議会などに繋いで、個別に相談を促します。
窓口が複数存在するため、どこに相談すべきか迷ったときは、まず訪問介護員に不安や疑問を伝えます。関係各所に繋いでもらい、必要なアドバイスや支援が受けられるようになります。
医療行為が必要になり、訪問介護員だけでは対応できない状況においても、かかりつけ医や救急病院へ連絡し、患者さんが適切なケアを受けられるように努めます。急変に備えて連絡体制を整えておくことも、訪問介護員の重要な役割です。
後悔なく末期ガンの在宅看取りを行うために
今回は、末期ガンに至るまでのステージについて、特徴や進行度、訪問介護の役割について紹介しました。
ガンの最終的な段階ともいえる終末期には、医療機関の利用率が多くみられます。しかし、患者さんの側からすると、病院ではなく在宅での看取りを希望するケースも少なくありません。そこで、近年では訪問診療や訪問介護サービスに注目が集まっています。
訪問介護は介護サービスを中心に提供する仕事ですが、関係各所やご家族との連携をとりながら患者さんに寄り添ったケアが可能です。後悔のない終末期ケアのためには、居宅サービスや訪問診療の情報を事前に集め、準備を進めていくことが大切です。
市川市・浦安市で訪問診療の受診をお考えの方は、
南行徳の面野医院 (訪問診療専用番号 047-321-4600)へご相談ください。