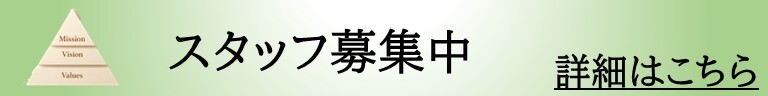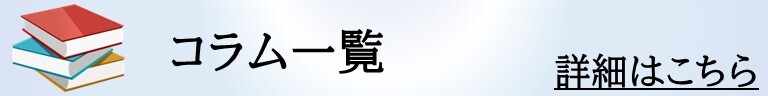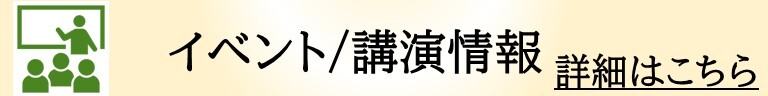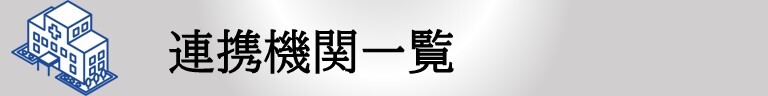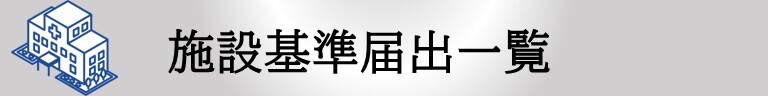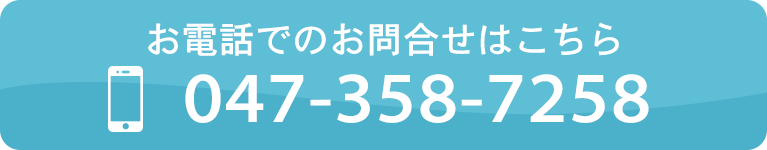認知症に対応した施設とは?費用が払えないときの対処方法を紹介
認知症は、脳の病気によって神経細胞の働きが低下し、記憶力や判断力が低下して認知機能全体が衰え、社会生活に支障をきたす状態です。
急性の病気ではなく徐々に進行するため、症状が軽いうちに施設への入居や認知症に対応した施設への転居を検討することが理想的です。
この記事では、認知症の方に対応した介護施設について紹介します。入居にかかる費用の目安・内訳と、費用が払えない場合の対策を紹介しています。ぜひ施設選びの参考にしてください。
介護施設の利用料は、前もって家賃を支払う「入居一時金」と、入居してから毎月家賃や食費をまとめて支払う「月額利用料」に分けられます。
入居一時金は前払い金としての性格をもちます。入居者が一定期間施設を利用するための権利を取得するために支払うお金で、入居期間中に償却されます。
月額利用料は、1ヶ月の生活にかかる費用の総額です。1ヶ月分の家賃や管理費・共益費、食費や生活サービス費を合算したものが毎月請求されます。
月額利用料の内訳は次のとおりです。
- 家賃(賃料)
- 管理費
- 共益費
- 水道・光熱費
- 食費(おやつ代)
- 生活サービス費
上記の費用は一例です。共益費の中に水道光熱費が含まれる場合や、食費とおやつ代が別に請求される場合などがあります。要支援・要介護以外の方は生活サービス費が発生するケースもあるため、施設ごとの料金体系を確認しましょう。
支払いが滞ると、滞納分の支払いや転居・退去を求められます。入居前に施設ごとの費用を計算し、月々にかかる費用を比較・検討することが大切です。
一部の施設では、支払いが可能かどうかの審査を行っています。審査がない場合は施設やケアマネジャーとよく相談し、負担の少ない施設を選びましょう。
入居一時金
入居一時金は、入居前に一定金額を支払い、入居期間中に施設側に支払われる(償却される)費用です。
元は家賃にあたる費用で、入居一時金として事前に支払っておくことで、その後の月額利用料の負担が軽くなります。
民間の企業や団体が運営する「民間施設」に多くみられ、地方自治体や社会福祉法人が運営する「公的施設」では入居一時金の負担がありません。
入居一時金が存在しない民間施設もありますが、代わりに敷金などとして数ヶ月分の家賃が徴収される場合があります。施設の料金体系をしっかりと確認することが大切です。
高級な施設では、数百万円から数億円になるケースもあります。入居一時金の1〜3割は入居後、早い段階で償却(初期償却)され、未償却分は事前に設定した入居期間の中で均等に償却されていきます。
想定入居期間を待たずに施設を退去・転居したときは、未償却分が返還金として返却されます。
月額利用料
月額利用料は、月々の生活にかかる費用です。家賃や管理費のほかに、介護施設では食費や水道光熱費も合算して請求する仕組みです。
民間施設は公的施設よりもサービスが行き届いているところが多く、その分費用も高くなる傾向にあります。公的施設は低所得者向けの施設も多く、安価に利用できる施設が揃っています。
施設の種類・月額利用料の目安は次のとおりです。
【施設の種類】
| 施設の種類 | 施設の分類 | 月額利用料の目安 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設) | 公的施設 | 約15万円 |
| 介護付き有料老人ホーム | 民間施設 | 約15万円〜 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 民間施設 | 施設によって異なる |
| グループホーム | 民間施設 | 約18万円 |
※上記は目安です。
認知症の方は、公的施設・民間施設の両方に入居できます。ただし、自立者向けの健康型有料老人ホームなど一部の施設では、認知症の方を受け入れられる体制が整っていないところもあります。事前に施設のホームページや問い合わせで確認しましょう。
施設の特徴やサービスにもよりますが、一般的な月額利用料の目安は15万円〜20万円前後です。一方、サービス付き高齢者住宅や有料老人ホームのような施設は料金体系が大きくことなることがあり、なかには1ヶ月に数十万円を超えるケースもあります。
認知症の方が入居できる施設
ここからは、認知症の方が入居できる施設を4ヶ所紹介します。
- 特別養護老人ホーム
- 介護付き有料老人ホーム
- サービス付き高齢者住宅
- グループホーム
特別養護老人ホームは公的施設で、介護付有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホームはそれぞれ民間施設です。
施設ごとの特徴と費用の目安をみていきましょう。
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム(特養)は、老人福祉法で「介護老人福祉施設」と定められた公的施設です。寝たきりの方や認知症によって介護を常に必要とする方を受け入れています。
原則的に要介護3以上の方を受け入れているため、食事・入浴・排泄の介助や健康管理など幅広いサポートを提供しています。認知症の方は要介護1,2からでも特例的に入居を認められる場合があります。(※1)
公的施設のため、入居一時金はかかりません。月額利用料の目安は15万円前後です。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、企業や団体が運営する民間施設です。
介護サービスが付帯するため、自立〜要介護までを受け入れています。原則として65歳以上から入居を申し込めますが、特定疾病として認知症がある方は、65歳に満たなくても入居できる場合があります。
配慮が行き届いた有料老人ホームの長所に、介護サービスが付帯していることで、さらに認知症の方に寄り添ったサポートを提供することができます。
入居一時金の有無や金額は施設により異なります。月額利用料も施設ごとに幅があり、15万円前後からが目安です。
サービス付き高齢者住宅
サービス付き高齢者住宅(サ高住)は、バリアフリー化を施した高齢者向けの住宅施設です。
介護施設ではなく住宅のため、自宅と同じように過ごせる自由度の高い施設として利用されています。介護サービスを利用する場合は、外部の介護サービス事業者と契約して利用します。
サ高住は居宅として利用する施設のため、要介護度が低い方の入居が多くみられます。認知症の方は、介護度が高くなったときのことも考えて入居を検討する必要があります。
入居一時金の有無や金額は施設により異なります。月額利用料の目安は15万円以上からが目安です。
グループホーム
グループホームは、地域密着型サービスとして利用されている民間施設です。
「認知症対応型共同生活介護」として、5〜9人の少人数で共同生活を送りながら、自立した日常生活を目指します。認知症について知識や経験をもつスタッフが24時間体制で入居者をサポートします。
病気に向き合いながら自立した生活を目指している方や、自宅のように身の回りのことをこなして生活を続けたい方に適した施設です。
入居一時金の有無や金額は施設により異なります。月額利用料の目安は15万円以上からが目安です。
介護施設の費用が払えなかった際に起きること
介護施設の費用が払えなかった場合は、猶予期間を設けてから退去が伝えられるか、身元引受人に滞納の件が伝えられます。
それぞれのケースについて、詳しく確認していきましょう。
猶予期間の後に退去になる
滞納が発生したときは、「猶予期間」と呼ばれる期間が1〜3ヶ月程度設けられます。この期間は身元引受人に連絡して滞納を解消するか、費用が安い施設への転居や退去について施設やケアマネジャーと話し合い、手続きを行う期間となります。
滞納が発生しそう、または発生したときは施設に連絡し、状況を伝えましょう。退去勧告までには一定の期間が設けられていますが、そのまま何もせずに過ごしていると強制退去になるおそれがあります。
施設の相談員や施設長、担当のケアマネジャーなど、知識のある相談員に滞納の件を伝えておけば、猶予期間中にできる解決策を一緒に考えてもらえるはずです。
身元引受人に連絡がいく
入居者に支払い能力がなくなったときは、身元引受人が代わりに費用を負担します。成年後見制度や保証会社が利用できる施設では身元引受人の登録が不要なため、滞納が発生した段階で担当者が対応します。
身元引受人が支払った場合は、滞納が解消されて入居を続けられます。身元引受人も支払いが困難な場合は、強制退去となる可能性があります。
施設の入居費用を抑える方法
施設の入居費用を抑えるためには、どのようなポイントに注意すれば良いのでしょうか。
- 入居一時金がない施設を選ぶ
- 相部屋を選ぶ
- 地方の施設を選ぶ
入居費用を下げる3つのポイントをみていきましょう。
入居一時金がない施設を選ぶ
入居一時金は、家賃を前もって一部支払うことで、入居後の負担を軽くできる仕組みです。施設によっては数十万円以上がかかることから、入居者への負担が大きくなります。
施設によって金額は異なるものの、数十万円〜数百万円、またはそれ以上のまとまった金額を前払いしなければならないため、入居後の生活に支障をきたす場合は、入居一時金がない施設を検討してください。
相部屋を選ぶ
相部屋は「多床室」と呼ばれ、1つの部屋に複数名が生活する居住形態です。
特別養護老人ホームや介護老人保健(老健)などでは多床室を用意している施設が多く、費用やサービス面で次のメリットが期待できます。
- 個室よりも費用が安い
- 患者同士で交流できる
- スタッフや患者の存在による安心感
費用が安いことはもちろんですが、個室で一人きりにならないため寂しくない、自然に会話が発生し賑やかな雰囲気の中で暮らせる点がメリットです。
認知症が進行したときも、一人きりになり発見が遅れる心配が少ないため、認知症に対応できる介護スタッフにすばやくサポートをしてもらえます。
地方の施設を選ぶ
東京などの大都市圏を中心に、利便性の高い場所にある施設は家賃や管理費が高くなる傾向にあります。民間施設よりも費用が安い公的施設は入居希望者が殺到し、空きがないといったケースも少なくありません。
一方、地方にある施設は都市部よりも費用が安く、のびのびとした環境の中で過ごせる点がメリットです。体験入居や施設への問い合わせ、見学などから住みやすさをチェックし、費用負担の少ない施設を選ぶことができます。
費用を払えない場合の対策
入居費用が支払えなくなった場合にできる対策方法は次の4つです。
- 施設の方に相談する
- 他の施設に移る
- 在宅介護を利用する
- 補助制度を利用する
さらに、対策方法の中で利用できる7つの制度もあります。
- 医療費控除
- 高額介護サービス費制度
- 介護保険の負担限度額認定制度
- 高額医療・高額介護合算制度
- 生活保護
- 利用者負担軽減制度
- 特定入所者介護サービス費制度
どのような制度が利用できるのか、詳しくみていきましょう。
施設の方に相談する
はじめに、入居中の施設の施設長やケアマネジャーに費用について相談しましょう。支払いができない可能性があること、転居の可能性があることを伝えて、解決策を一緒に考えてもらいます。
支払いができないからといって、すぐに退去を迫られる心配はありません。施設によっては支払日の延期や分割払いにするといった対応もとられています。(※)
※施設の方針や規約によっては不可の場合があるため、施設にお問い合わせください。
他の施設に移る
支払いが難しく、継続して住み続けられないときには、他の施設への転居を検討します。
- 入居一時金がかからない
- 家賃や管理費が安い
- 複数のプランを用意している
費用の負担が少なく、必要なサポートが受けられる転居先をチェックします。
入居一時金がかからない(または入居一時金が安い)、家賃や管理費が安く月額利用料がかからない施設を中心に探します。
民間施設から転居する場合は、費用が安い公的施設を検討することもできます。
在宅介護を利用する
施設では手厚いサポートが受けられますが、相応の費用がかかります。入居を継続できない場合には、在宅介護を検討しても良いかもしれません。
在宅介護は、24時間介護スタッフによる見守りは受けられませんが、プライバシーが守られる自宅で老後を過ごせる方法です。
デイサービスや訪問介護、ショートステイを組み合わせた「小規模多機能型居宅介護」を利用すれば、自宅にいながら介護サービスを利用できます。(※)
※参照元:厚生労働省「どんなサービスがあるの? - 小規模多機能型居宅介護」https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group11.html
補助制度を利用する
国や地方自治体では、介護にかかる費用負担を軽減する補助制度を設けています。支払いが難しい場合は、介護費用の補助制度を利用しましょう。
制度ごとに対象者の条件や申請に関するルールが設けられていますので、申請できるかどうかを確認のうえ、申し込みを検討してください。
医療費控除
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)にかかった医療費が一定の金額を超えたときに適用される所得控除の一種です。
給与所得者を対象とした制度ですが、生計を同じにする配偶者やその親族に医療費を支払った場合は、その所得者に医療費控除が適用されます。
認知症のご家族が施設に入居したときは、介護サービス費や医療費を一定額以上支払った場合に控除が受けられます。
※参照元:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
高額介護サービス費制度
高額介護サービス費制度は、1ヶ月に支払った介護保険サービス費の自己負担額(1〜3割)が一定の上限額を超えたときに、超過分が還付される制度です。(※)
介護保険サービス費と医療費の自己負担額について、8月1日〜翌7月31日までの分を合算して、窓口で申請します。ただし介護施設でかかった家賃や食費は合算できません。
※参照元:厚生労働省「サービスにかかる利用料」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
介護保険の負担限度額認定制度
介護保険の負担限度額認定制度は、住民税非課税の方が「介護保険負担限度額認定証」の認定・交付を受けることで、介護サービス費・介護施設の居住費・介護施設の食費・生活費の負担を軽減できる制度です。
制度の対象となる介護施設は、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院などの公的施設が中心です。短期入所療養介護などのショートステイも含まれます。(※)
※参照元:町田市「「介護保険負担限度額認定制度」について」
https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/kaigo/hutan/hutangendogaku.files/2024futangendogaku.pdf
高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度(高額介護合算療養費制度)は、1年間(8月1日~翌7月31日)の医療保険・介護保険の自己負担額が高額になったときに、負担分が軽減される制度です。(※)
在宅介護を受けている方は、ショートステイやデイサービスなどの「居宅サービス」が制度の対象になります。特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設に入居する方が受ける「介護施設サービス」や、「地域密着型サービス」も対象に含まれます。
※参照元:厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」
生活保護
生活保護は、生活に困窮する人が保護を受けられる制度です。住宅扶助や生活扶助を受けることができ、「健康で文化的な最低限度の生活」が保障されます。(※)
※公的施設・民間施設のいずれも生活保護受給者の受け入れを行っていますが、受け入れの可否は施設によって異なるため、詳細は個別にご確認ください。
※参照元:厚生労働省「福祉・介護生活保護制度」
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/10-2/kousei-data/PDF/22010809.pdf
利用者負担軽減制度
利用者負担軽減制度とは、地方自治体や社会福祉法人が運営する公的施設に入居したときや在宅介護中の方がショートステイを利用したときに、負担額の25%(老齢福祉年金受給者は50%)が軽減される制度です。(※)
※軽減の対象となる事業者は限定されているため、市や事業者にご確認ください。
※参照元:船橋市「社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度について」
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kaigo/004/p010099.html
費用を払えない場合の対策
認知症は、脳の病気によって生活に支障をきたす病気です。認知機能も衰えるため、症状が進行すると周囲のサポートが必要になることもあります。
認知症受け入れ可能な施設では、認知症を含めさまざまな疾患に知識をもつスタッフが常勤し、医療機関とも連携しています。一人で健康上の悩みや不安を抱え込む心配がなく、他の入居者とのコミュニケーションの機会もあります。(※)
在宅での介護やケアが受けられない場合は、症状と上手に付き合うためにも、周囲の力を借りて生活が続けられる施設を探してみてはいかがでしょうか。
※参照元:政府広報オンライン「知っておきたい認知症の基本」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201308/1.html
市川市・浦安市で訪問診療の受診をお考えの方は、
南行徳の面野医院 (訪問診療専用番号 047-321-4600)へご相談ください。
📞047-321-4600からお電話でも受付中(診療時間内)
訪問診療についてのお問い合わせはこちら