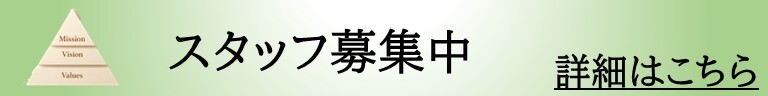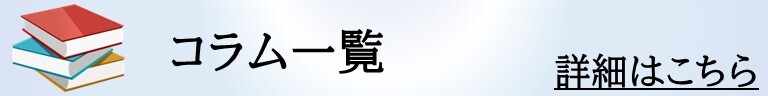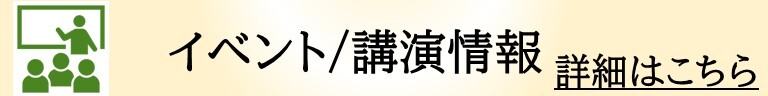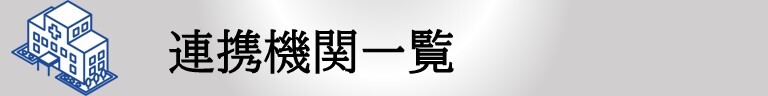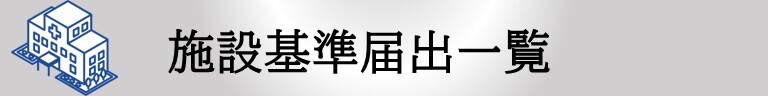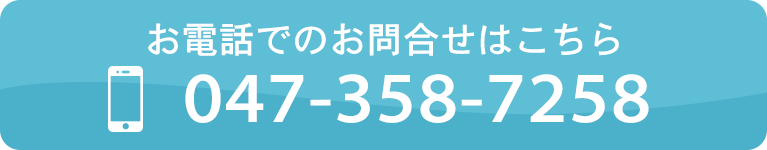認知症対応の介護施設を選ぶ方法と入居にかかる費用相場を紹介
認知症は、脳の病気によって認知機能が衰え、社会生活に支障をきたす病気です。
症状が進行すると24時間のサポートが必要になり、介護施設を中心に入居を検討することになります。介護サービスを提供している施設には公的・民間の違いや料金体系・サービスの違いがあるため、施設ごとの特徴を押さえておきましょう。
ここでは、認知症の介護施設を選ぶ方法や費用の相場を紹介します。施設の探し方やポイントも取り上げています。ぜひ施設選びの参考にしてください。

介護施設の入所にあたってかかる費用
介護施設の入居費用は、「入居一時金」と「月額利用料」に分けられます。
入居一時金は、入居時のみにかかる費用です。月額利用料は、賃料や管理費といった月々の費用に加えて、水道光熱費や食費といった項目を合算した費用です。
入居一時金は1回のみの費用ですが、月額利用料は入居期間中毎月支払う費用です。毎月一定の費用がかかる料金で、内訳は次のとおりです。
- 家賃(賃料)
- 管理費
- 共益費
- 水道・光熱費
- 食費(おやつ代)
- 生活サービス費
共益費がない施設や、水道光熱費を個別に請求する施設もあり、料金体系は施設ごとに異なります。生活サービス費は自立者のみ(要支援・要介護の方は支払い不要)になるケースもあります。
月額利用料は毎月発生する費用です。支払いが滞ってしまうと、滞納分の支払いを求められます。それでも支払いが難しければ身元引受人への支払い催促、または入居者の転居や退去となります。
一部の施設では、事前に入居者や身元引受人の状況をチェックし、支払いが可能かどうかの審査を行っています。施設側と相談して決めることもできますので、入居にかかる費用は早い段階から考えておきたいところです。
ここからは、入居一時金と月額利用料についてみていきましょう。
入居一時金
入居一時金は、入居期間中に分割して施設に支払われる(償却される)費用です。
月額利用料の賃料にあたる費用で、入居一時金を支払っておくと、月額利用料の賃料負担分が軽くなります。特別養護老人ホームや介護医療院のように入居一時金が存在しない施設もありますが、公的施設の一部と民間施設の多くは、入居一時金を設定しています。
費用は施設ごとに異なり、数十万円から数億円になるケースもあります。入居一時金の多くは、支払った分の1〜3割が入居してからすぐに償却(初期償却)されます。初期償却を終えると、残りのお金は事前に設定した入居期間の中で均等に償却される仕組みです。
設定された期間を待たずに施設を退去、または転居したときは、未償却分のお金は返還金として返却されます。
月額利用料
施設に入居すると、一般的な賃貸物件と同じように毎月の家賃・管理費が発生します。食費や水道光熱費も利用した分加算されます。料金体系は施設ごとに異なり、立地やサービス内容、居室のタイプ・グレードによって異なります。
月額利用料の目安は施設の種類によって違いがあり、地方自治体や社会福祉法人が運営する公的施設では費用が安く抑えられています。民間の企業・団体が運営する民間施設はサービスが行き届いていますが、公的施設よりも費用が高い傾向にあります。
施設の種類・月額利用料の目安は次のとおりです。
【施設の種類】
| 施設の種類 | 施設の分類 | 月額利用料の目安 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設) | 公的施設 | 約15万円 |
| 介護付き有料老人ホーム | 民間施設 | 約15万円〜 |
| グループホーム | 民間施設 | 約18万円 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 民間施設 | 施設によって異なる |
| 住宅型有料老人ホーム | 民間施設 | 約12〜30万円 |
※上記は目安です。
認知症の方は、公的施設・民間施設どちらでも入居できます。月額利用料の目安は15万円から20万円前後です。一方、サービス付き高齢者住宅のように施設ごとの幅が大きく、数十万円を超える利用料がかかるケースもあるため、事前に料金体系を確認してください。
また、公的施設の多くは入居一時金が不要ですが、ケアハウスのように料金が発生する施設もあります。入居一時金を支払うことで月額利用料が安くなりますが、民間施設では100万円を超えるケースもあります。
賃料
賃料は、入居した施設や居室の利用にかかる費用です。施設の立地・グレード・ケア体制・サービス内容によって費用が変わります。
公共交通機関が充実していたり都心部にあったりといった利便性の高い場所にある施設のほか、完全個室・24時間体制のケアが受けられる施設では、賃料が高額になる傾向です。公的施設よりも民間施設のほうがサービス面では充実しており、そのぶん費用も高くなります。
公的施設は、月々の「基準費用額」が定められています。基準を元にして賃料が決まるため、民間施設ほどの費用差はありません。
居室は、「多床室」と呼ばれる相部屋タイプほど安く、個室がもっとも高くなります。種類は個室・ユニット型・多床室の3タイプで、多床室は2〜4人が1つの部屋で共同生活を送ります。
管理費
管理費は、施設の維持管理や設備費として使われる費用です。入居者全員が管理費を支払い、施設の運営を支えます。
高齢者向け住宅や介護施設は、居室以外にもさまざまなスペースが併設されています。共有スペースと呼ばれる廊下やホール、食事スペースやリハビリテーション室はその一例です。
共有スペースは施設のスタッフが管理するため、人件費にも管理費が使われます。家賃と同じく施設によって相場が異なるので、事前に料金体系を調べておきましょう。
水道・光熱費
水道光熱費は、施設で使用した水道・電気・ガスの料金です。電話代やインターネット料金が含まれる場合もあります。
一般の賃貸物件と同じく、公的施設・民間施設のどちらに入居しても発生する費用です。個室タイプの居室ではメーターが取り付けられているところもあります。毎月の使用量を計量し、入居者自身で負担します。
施設によっては、水道・光熱費と区別せずまとめて計上し、請求する場合があります。管理費や共益費といった名目で含まれている場合もあるので、施設ごとに費用を計上、請求方法を確認しておきましょう。
食費
食費は、施設内での食事にかかる費用です。朝・昼・夜のそれぞれを食べた回数分請求される仕組みです。
住宅型有料老人ホームのように、入居者自身で調理する形式の施設では各人が食材を調達するか、施設に食費を支払って食事の提供を受けます。認知症の方の場合、認知症の進行度によっては自力で調理ができないため、食事の提供が行われる施設に入居することになります。
食事は、入居者の健康状態に合わせて提供されます。病気の方の療法食、アレルギーや減塩への対応のほかに、介護状態の方は刻み食やミキサー食といった形態の食事も提供されます。
季節ごとのイベントや誕生日、年末年始には特別メニューになるため、追加費用がかかることもあります。食費の内訳も事前に確認しておきたいポイントです。
支払い方法
認知症の方が入居する施設では、「月払い型」「全額前払い」「一部前払い型」の支払い方法が選択できます。
月払い型
月払い型は、家賃を入居一時金として前払いせずに、本来の賃料を毎月支払う方式です。
入居一時金がかからないぶん、月額利用料は本来の賃料を毎月支払っていくため、月額利用料が割高になります。入居一時金を支払っておけば、月額利用料の負担を小さくできますが、前もって持ち出しを多くしたくない場合は月払い型がおすすめです。
注意点として、施設の月額利用料が値上げになった場合、負担も値上げに応じて大きくなります。入居後に支払いが難しくなり転居を余儀なくされるケースも考えられるため、月払い型を検討している方は入居したい施設ごとの月額費用を計算し、比較しておく必要があります。
全額前払い型
全額前払い型は、入居にかかる費用を一括で支払う方法です。一度に支払いを終えられるので、入居後は追加費用の心配がなく持ち出しも最小限に抑えられます。入居後の生活を想定し、先にすべて支払っておきたいという方に適しています。
全額前払い型は事前に入居期間を想定して(想定居住期間)、その分の家賃を前払いする方式です。想定居住期間は、入居者の平均余命などを参照して設定します。
一部前払い型
一部前払い型は、入居時に想定居住期間の賃料を一部前払いして、残りの分を入居後に月々支払っていく方法です。
月払い型のように月々の負担が大きくならず、全額前払い型のように持ち出しが多くならないため、2つの支払い方式の間をとった方法といえるでしょう。
認知症の方が入居できる施設
認知症の方が入居できる施設は、公的施設・民間施設をあわせて次の5つです。
- 特別養護老人ホーム
- 介護付き有料老人ホーム
- グループホーム
- サービス付き高齢者住宅
- 住宅型有料老人ホーム
それぞれの施設の特徴と費用の相場をみていきましょう。
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム(特養)は、介護老人福祉施設という正式名称で、寝たきりの方や認知症により常に介護を必要とする方のための施設です。
日常生活において常時介護を必要とし、自宅で介護を受けられない方を受け入れています。食事や入浴、排泄の介助や移乗、健康管理といったサポートを行っています。原則的に要介護3から入居可能ですが、認知症がある方は要介護1,2でも特例的に入居を認められる場合があります。(※1)
費用相場
特別養護老人ホームは公的施設のため、入居一時金はかかりません。月額利用料も、要介護の程度と所得の状況に応じた所得段階に応じて金額が変わります。
一例として、要介護3で介護保険1割負担、所得段階が第3段階の方(住民税非課税世帯)が入居したときの費用相場の例は次のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 介護保険自己負担額 | 約25,000円 |
| 食事負担額 | 約20,000円 |
| 居住費 | 約30,000円(従来型多床室は11,000円) |
| 合計 | 約75,000円 |
※上記は一例です。
合計金額に加えて「家電製品持ち込み料」や「認知症行動緊急対応加算」のように、個々の入居者の状況に応じた料金が加算されます。
※1参照元:札幌市「介護保険による入所施設」
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k100citizen/k142_6sisetu.html
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、民間の企業や団体が運営する民間施設です。
認知症がない方でも、65歳以上の高齢者であれば入居を申し込むことができます。原則的に終身利用となりますが、介護度が重くなってもそのまま入居を続けられます。
介護付き有料老人ホームは、有料老人ホームのサービスに加えて、介護サービスを提供している施設です。(※1)
高齢者かつ要介護1以上の方が入居できる施設で、特定疾病として認知症の診断を受けている場合は、65歳以下でも入居できます。
費用相場
介護付き有料老人ホームは民間施設です。入居一時金は施設によって異なり、無料または「敷金」として前納する場合もあります。
月額利用料は、要介護の程度に応じて金額が変わります。一例として、要支援1〜要介護5までの方が個室に入居した際の費用相場の例は次のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 家賃相当額 | 約75,000円 |
| 食事負担額 | 約30,000円 |
| 管理費 | 約35,000円 |
| 生活サポート費 | 0円 |
| 合計 | 約140,000円 |
※上記は一例です。
自立者も受け入れている施設では、自立のみ生活サポート費に費用がかかる場合があります。また、上記の項目に加えて水道光熱費が別途計上される施設もあります。
※1参照元:厚生労働省「介護を受けながら暮らす高齢者向け住まいについて」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000038005_1.pdf
グループホーム
グループホームは、介護保険制度上「認知症対応型共同生活介護」として、5名以上の少人数で生活し、ケアやサービスが提供される施設です。
急性を除く認知症の高齢者を対象に受け入れている施設で、集団生活を送りながら自立を目指します。
要支援2〜要介護5までの方が入居できる施設で、入居者は要支援・要介護度が低いうちからできることを自身で行います。機能訓練や日常生活のサポートを受けながら、能力に応じて自立した生活が営めるように努めます。(※1)
費用相場
グループホームは民間施設です。入居一時金は施設によって異なりますが、公的施設と違い無料ではないため注意が必要です。
月額利用料は、要介護の程度に応じて金額が変わります。要支援1〜要介護5までの方が入居する場合の費用相場の例は次のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 家賃相当額 | 約60,000円 |
| 食材費 | 約40,000円 |
| 管理費 | 約20,000円 |
| 水道光熱費 | 約15,000円 |
| 合計 | 約135,000円 |
サービス付き高齢者住宅
サービス付き高齢者住宅(サ高住)は、一定の広さの居室や設備を整え、バリアフリー化が施された高齢者向け住宅です。
サ高住は介護施設ではなく住宅という位置づけのため、プライバシーに配慮された生活を送ることができます。
すべての施設で安否確認(状況把握)と生活相談サービスを提供し、入居者が個々に食事の提供や入浴などの介護サービスを契約して生活を送ります。介護福祉士や介護支援専門員といった有資格者が見守りを行います。(※1)
費用相場
サービス付き高齢者住宅は民間施設です。入居一時金は施設によって異なりますが、公的施設と違い無料ではないため注意が必要です。
月額利用料は、要介護の程度と所得の状況に応じた所得段階に応じて金額が変わります。サービス付き高齢者向け住宅向け住宅は民間施設ですが、入居一時金が無料のところもあります。
入居にかかる費用相場の例は次のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 家賃 | 50,000円~ ※居室のタイプにより異なる |
| 食費 | 44,000円 |
| 共益費 | 15,000円 |
| 管理費 | 21,000円~ ※居室のタイプにより異なる |
| 合計 | 約130,000円~ |
※上記は一例です。
この例では入居一時金はかかりませんが、光熱費が共益費に含まれるか、別途請求になるかは施設によって異なります。また、月額利用料に介護保険自己負担額を含んだ金額が請求されます。
※1参照元:厚生労働省「サービス付き高齢者向け住宅について」https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish_sumai/
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、民間の企業や団体が運営する民間施設です。生活支援などの基本的な有料老人ホームのサービスを提供している、高齢者向けの居住施設です。(※1)
施設によって入居条件は異なりますが、65歳以上の高齢者を中心に入居を受け入れています。認知症のように特定疾病の方は、65歳以下でも申請が行えます。
費用相場
住宅型有料老人ホームは民間施設です。入居一時金は施設によって異なり、無料または「敷金」として前納する場合もあります。
月額利用料は、要介護の程度に応じて金額が変わります。有料老人ホームは民間施設ですが、入居一時金が無料になるところもあります。一方で、敷金として家賃3ヶ月分程度の費用がかかるケースもみられます。
住宅型有料老人ホームの利用者が介護居室に入居した際の費用相場は次のとおりです。(※2)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 家賃 | 約90,000円 |
| 食費 | 約57,000円 |
| 管理費 | 約48,000円 |
| 合計 | 約195,000円 |
※上記は一例です。
住宅型有料老人ホームは自立者を受け入れているところが多いため、自立者のみ生活サービス費が別途かかることもあります。
上記の費用に加えて、水道光熱費や介護保険自己負担額や実費分の費用が加算されます。
※1参照元:厚生労働省「有料老人ホームの類型」
施設の入居費用を抑える方法
施設への入居にかかる費用を減らすためには、3つのポイントを確認してください。
- 入居一時金がない施設を選ぶ
- 相部屋を選ぶ
- 地方の施設を選ぶ
なぜ費用を抑えられるのか、ポイントごとに詳しくみていきましょう。
入居一時金がない施設を選ぶ
入居一時金は、事前に家賃を支払うことで月額利用料を軽くするシステムです。しかし、事前に支払う費用の負担が大きくなるため、入居後に余裕がなくなってしまうケースもあります。
施設への入居に費用をかけたくない場合は、入居一時金がない施設を選びましょう。
相部屋を選ぶ
相部屋は「多床室」と呼ばれており、1つの部屋に複数名が居住する住居形態です。
プライベートな個室空間ではありませんが、仕切りやカーテンで区切ってスペースを確保することができます。入居時だけではなく入居後も費用負担を抑えたいときは、個室ではなく相部屋を検討してみてください。
地方の施設を選ぶ
首都圏や大都市の中心部、公共交通機関に近い利便性の高い場所は、いずれも立地条件が良いため家賃や管理費が高くなります。一方、地方では都市部でも比較的費用が安く、郊外地域ではさらに安くなる可能性があります。
補助制度
認知症の方が施設に入居する際に利用できる補助制度は次のとおりです。
- 医療費控除
- 高額介護サービス費制度
- 介護保険の負担限度額認定制度(特定入所者介護サービス制度)
- 高額医療・高額介護合算制度
- 生活保護
- 利用者負担軽減制度
- 在宅介護
8つの制度やサービスについて、詳しくみていきましょう。
医療費控除
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)の医療費が10万円を超えたときに所得控除が受けられる制度です。(※)
※参照元:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
高額介護サービス費制度
高額介護サービス費制度は、公的介護サービスに支払った金額の合計が一定額を超えたときに、超過分が払い戻される制度です。(※)
※参照元:厚生労働省「サービスにかかる利用料」
介護保険の負担限度額認定制度(特定入所者介護サービス制度)
介護保険の負担限度額認定制度(特定入所者介護サービス制度)は、介護保険施設の利用時に受けるサービスについて、低所得要件を満たした場合に所得ごとの限度額と照らし合わせて、食費と居住費が軽減されます。(※)
※参照元:松戸市「介護保険負担限度額認定について」
高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度(高額介護合算療養費制度)は、医療保険と介護保険における1年間(8月1日~翌7月31日)の自己負担のうち、合計額が高額になった場合に自己負担が軽減される制度です。(※)
※参照元:厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」
生活保護
生活保護とは、生活に困窮する国民が程度に応じて保護を受けられる制度です。住宅扶助や生活扶助を通して「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するために設けられています。(※)
※参照元:厚生労働省「福祉・介護生活保護制度」
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/10-2/kousei-data/PDF/22010809.pdf
利用者負担軽減制度
利用者負担軽減制度とは、地方自治体や社会福祉法人が運営する公的施設に入居したとき、または在宅介護を受ける方がショートステイを利用した際に、利用者負担額の25%(老齢福祉年金受給者は50%)を軽減する制度です。
低所得の方でも介護保険サービスを利用できるように、負担額を軽減するための制度です。軽減の対象となる事業者は限定されているため、市や事業者にご確認ください。(※)
※参照元:船橋市「社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度について」
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kaigo/004/p010099.html
在宅介護を利用する
在宅介護は、介護医療院などの医療機関や施設を利用せずに、自宅で介護サービスを利用する方法です。施設の利用料がかからず、治療に専念しやすい点がメリットです。(※)
※参照元:厚生労働省「在宅医療・介護の推進について」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/dl/zaitakuiryou_all.pdf
施設の探し方
入居先の施設は、知人や身内からの紹介や役所・役場への相談など、さまざまな方法があります。ここでは、インターネットで検索する方法と、地域包括センターへの相談で探す方法についてみていきましょう。
インターネットで探す
インターネットでは民間の事業者が運営するサイトと、国や地方自治体が運営する公的なサイトがあります。どちらも情報収集に役立ちます。
厚生労働省では、「介護事業所・生活関連情報検索」というホームページを公開しています。サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームの検索、認知症に関する相談窓口や薬局といった幅広い情報が検索できます。(※)
※参照元:厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索」
地域包括支援センターに相談する
地域包括支援センターは、福祉・介護に関する相談先の一つです。認知症を抱える方ご自身と、ご家族や身元引受人の方の相談を受け付けています。
介護が必要になったときに相談できる窓口ですが。将来的に介護が必要になる可能性があるときにも相談できます。健康や福祉、介護の専門家が相談を受け付けていますので、施設探しで困ったときはお近くのセンターにご相談ください。
※参照元:厚生労働省「認知症に関する相談先」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076236_00003.html
施設の探し方
入居施設を選ぶ際に意識したいポイントは次の6つです。
- 入居する方と一緒に見学する
- スタッフの知識や対応を確かめる
- 施設全体の雰囲気を確かめる
- 過去の退去事例を確かめる
- 希望通りの暮らしができそうか確かめる
- 体験入居してみる
事前の見学や退去事例の確認など、選び方のポイントごとに詳しく確認していきましょう。
入居する方と一緒に見学する
入居する施設は、ホームページやパンフレットの情報だけではなく見学や体験入居で確認しましょう。入居者が健康で、自分の意思で施設を決められるときには、ご家族だけではなく入居者ご自身でも希望する施設を訪れることが大切です。
スタッフの知識や対応を確かめる
施設スタッフが認知症についての知識や経験をもっているかを確認しましょう。認知症専門の介護施設では確認の必要はありませんが、どのようなサポートを受けられるのか相談しておくと安心です。
施設全体の雰囲気を確かめる
施設全体の雰囲気は、見学や体験入居の際に慎重に確認したいポイントです。設備や住みやすさのほかにも、入居者同士の雰囲気やスタッフの雰囲気、連携体制といった部分を中心にチェックします。
過去の退去事例を確かめる
過去に退去が発生した事例を確認しておくことで、どのようなトラブルがあったのかを把握できます。入居後に同じようなトラブルに巻き込まれてしまうリスクを予防できます。
希望通りの暮らしができそうか確かめる
施設ごとの設備やサービス、1日のスケジュールから、希望通りの暮らしが送れるかをイメージしましょう。緊急時に頼れるスタッフの確認や相談室・医務室の有無、医療機関への連絡方法も想定しておくことが大切です。
体験入居してみる
体験入居が可能な施設では、実際に1日を過ごしてみることで空気感を確認できます。多忙な時期には難しくなる場合もあるため、早めに体験入居ができないか確認しておきましょう。
施設への入居にあたって考え得るトラブル
施設への入居にあたり、「認知症の方が入居を拒否する」「施設の退去を求められる」という2つのトラブルに注意が必要です。
認知症の方が入居を拒否する
認知症になると、認知機能が低下するため自身が病気であると認識しにくくなります。「自立した暮らしを続けたい」という思いから、入居を拒否する可能性があります。
施設の退去を求められる
入居者自身が滞納や施設内でトラブルを起こしたり、施設の運営者に問題が起きたりしたときには、退去を求められる可能性があります。認知症の症状が進行していくことを考えて、適切なケアが受けられる環境を選びたいところです。
在宅介護とは
在宅介護とは、自宅にいながらにして介護を受ける方法です。
ご家族からケアやサポートを受けますが、必要に応じてホームヘルパーによる訪問を受けて介護サービスを利用したり、ご自身でデイサービス(通所介護)を利用したりして、必要な介護や機能訓練を受けます。
認知症に適した施設・費用の内訳や選び方を確認
今回は、認知症の方が利用できる施設の種類と費用の内訳、利用可能な制度を紹介しました。
認知症にかかると、症状は少しずつ進行します。早めに治療を開始し、ご自身で自立した生活を目指すことが大切ですが、一定以上症状が進んでくるとケアやサポートを必要とします。
早めに自宅以外の施設や住環境を選んでおくことで、将来に備えながら病気とも向き合いやすくなるでしょう。在宅介護を検討する場合は、訪問診療や通所介護のような方法もあわせて検討しましょう。
市川市・浦安市で訪問診療の受診をお考えの方は、
南行徳の面野医院 (訪問診療専用番号 047-321-4600)へご相談ください。
📞047-321-4600からお電話でも受付中(診療時間内)
訪問診療についてのお問い合わせはこちら