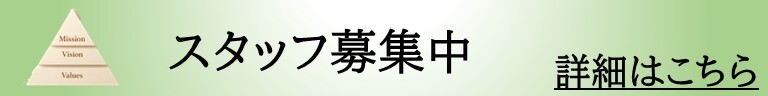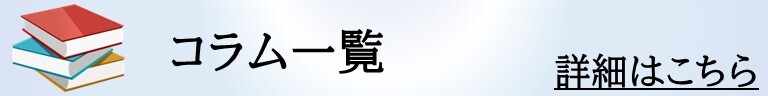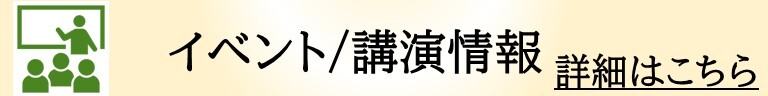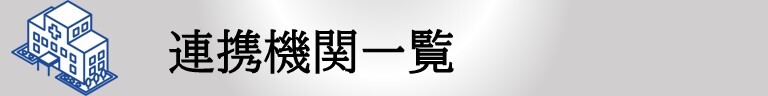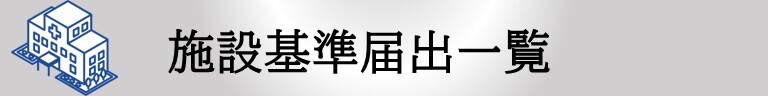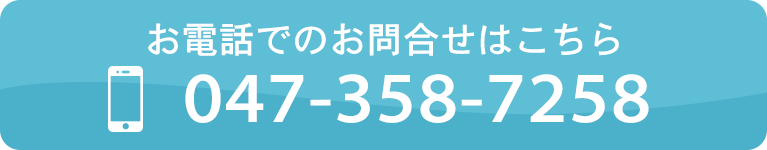認知症の方を施設に入れる際にお金がないときの対策と利用可能な制度
認知症は、脳の認知機能が病気によって低下し、社会生活に支障をきたす病気です。健康な状態から徐々に症状が進行し、記憶や思考、理解力などが低下していきます。要介護度が高くなると、ご家族だけではサポートが難しくなることもあります。
自宅以外では、介護施設やグループホームなどの施設に入居することができます。「特定疾病」として認定されると、高齢に達していなくても入居が認められます。
この記事では、お金がない場合でも認知症の方が施設に入居する方法や施設の選び方を紹介します。入居費用を抑えるポイントや補助制度も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
認知症の方は、国や地方自治体が運営する「公的施設」と、民間の企業や団体が運営する「民間施設」の両方に入居できます。
入居できる施設の一例は次のとおりです。
- 特別養護老人ホーム
- 介護付き有料老人ホーム
- グループホーム
- サービス付き高齢者住宅
特別養護老人ホームは公的施設、介護付き有料老人ホーム・グループホーム・サービス付き高齢者向け住宅はいずれも民間施設です。どのような施設なのか、詳しくみていきましょう。
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム(特養)は、要介護度の高い高齢者や認知症の方を受け入れている公的施設です。
在宅での生活が困難な方に、入浴・排泄・食事・身の回りの世話・掃除や洗濯・機能訓練といった生活全般のサポートを提供しています。
入居対象者は原則として65歳以上(要介護3)からですが、認知症に該当する方は特例により要介護1〜2でも入居が認められることがあります。詳細は入居を希望する特別養護老人ホームにご確認ください。
※参照元:厚生労働省「介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000663498.pdf
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、介護サービスが付帯する民間施設です。
自立または要支援から受け入れており、要介護レベルはもっとも重度の要介護5にも対応しています。民間施設のため、公共施設よりも費用は高い傾向にありますが、居室を広くとるなどの配慮が行き届いています。
特別養護老人ホームは原則65歳以上からの入居となっていますが、介護付有料老人ホームは60歳から入居できるケースが多くみられます。
※参照元:厚生労働省「有料老人ホームの類型」
https://www.mhlw.go.jp/content/001256555.pdf
グループホーム
グループホームは、認知症の方が共同で生活を送りながら、自立した生活を目指すための民間施設です。
施設には24時間体制で専門のスタッフが常駐しています。スタッフのサポートを受けながら入居者それぞれが家事や炊事などをこなします。
入居者は家庭的な環境の中で日常生活を送ります。原則として個室が義務付けられているので、プライバシーが確保できます(介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援2以上から利用できます)。
※参照元:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group18.html
サービス付き高齢者住宅
サービス付き高齢者住宅は、自立〜要介護度が低い方や高齢者向けの住宅であり、民間施設の一種です。
自宅のように暮らせる居住施設のため、特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームのように施設のスタッフが直接介護を行うことはありません。
介護が必要な場合は外部の介護サービスと契約をする必要がありますが、介護施設ほどの制約を受けず自宅のような感覚で自由に過ごすことができます。
※参照元:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索「サービス付き高齢者向け住宅について」https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish_sumai/
施設の選び方
認知症の方が施設を選ぶときは、次のポイントを確認してみてください。
- 予算を決める
- 事前に見学する
- 通いやすい距離の施設を選ぶ
- 家族と話し合う
ここからは、4つの選び方についてみていきましょう。
予算を決める
施設の入居にかかる費用は、入居前の「入居一時金」と、入居後の「月額利用料」です。
月額利用料は、固定でかかる家賃や食費などの費用に加え、理美容費や介護サービス費、送迎などのオプションサービスにかかった分が加算されます。
収入や貯蓄、年金などの準備できるお金から予算を決めて、無理のない計画をたてることが大切です。
事前に見学する
2ヶ所以上の施設を選び、事前に見学を行いましょう。「公的施設か民間施設か」「介護施設か高齢者向け住宅か」を考えるためにも、複数の施設を見て雰囲気を確かめることをおすすめします。
基本料金や施設の雰囲気、設備や広さ、過ごしやすさといったポイントのほかに、オプションで選べるサービスや食事の内容・種類、医療機関(かかりつけ医)との連携体制も見ておく必要があります。入退去時のルールや費用については事前にしっかりと確認しておきましょう。
通いやすい距離の施設を選ぶ
施設の住みやすさや料金に加えて、立地条件や自宅からの距離、アクセス性も確認しましょう。
- 自宅から近い場所
- 今までの生活圏内にある
- 車や公共交通機関で通いやすい
住んでいた場所から遠すぎると、家族や知人が面会にやってくるまでに時間がかかることがあります。施設の間取りや広さだけではなく、通いやすい場所にあるかどうかを確認してください。
家族と話し合う
施設の立地条件・料金・サービス内容などに満足できたら、入居者とご家族でよく話し合って入居先を絞り込みます。
見学や体験入居を経て、候補となった1ヶ所の施設を選びます。入居者ご自身とご家族の希望が合わなければ、専門的な知識をもつケアマネジャーや信頼のできる第三者にも相談してみましょう。
施設の入居費用を抑える方法
入居費用を抑えるために役立つ方法をみていきましょう。
- 入居一時金がない施設を選ぶ
- 相部屋を選ぶ
- 地方の施設を選ぶ
それぞれ、費用の節約にどのような効果が期待できるのでしょうか。
入居一時金がない施設を選ぶ
入居一時金とは、施設への入居にかかる費用のうち、入居前に支払う家賃のことです。
家賃の前払い金としての性格をもつもので、施設により相場に違いがあります。入居一時金がかからない施設もありますが、「敷金」として前払いが必要な場合は注意が必要です。
相部屋を選ぶ
相部屋は、1つの部屋に複数名がベッドを置いて寝泊まりする形態で「多床室」と呼ばれています。2〜4人部屋が主流で、個室よりも金額が安いため、月額利用料のうち固定費である家賃が安く抑えられます。
施設の利用料が高額な場合は、相部屋を検討するのも一つの方法です。
地方の施設を選ぶ
都市部や利便性の高い場所にある施設は、立地条件の良さから家賃などが高くなる傾向にあります。
一方、地方の施設は都会の施設よりも低価格で、安く入居できるところが多く見つかります。公的施設は民間施設よりも低価格なため、費用負担の少ない施設が探しやすいでしょう。
施設に入れるお金がない場合に活用したい補助制度
施設に入れるお金がない場合に活用したい補助制度は次の4つです。
- 高額介護サービス費制度
- 医療費控除
- 介護保険の負担限度額認定制度
- 高額医療・高額介護合算制度
それぞれの制度にはどのような特徴があるのでしょうか。詳しくみていきましょう。
高額介護サービス費制度
高額介護サービス費制度は、介護保険サービスを利用したときに支払った自己負担額(1〜3割)が一定の上限額を超えたときに、超過分が申請によって還付される制度です。(※)
対象となるサービスは、在宅介護を受けている方が利用するショートステイやデイサービスなどの「居宅サービス」、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設に入居する方が受ける「介護施設サービス」と、「地域密着型サービス」です。
介護施設サービスは、食事や入浴などの介助や看護が含まれます。ただし、食費や家賃、生活費は対象外です。福祉用具の購入費や差額ベッド代も含まれません。
※参照元:厚生労働省「サービスにかかる利用料」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
医療費控除
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が基準額を超えたとき、確定申告によって超過分が還付される所得控除の一種です。
給与所得者を対象とした制度ですが、生計を同じにする配偶者やその親族に医療費を支払ったときは、所得者が医療費控除を受けられます。施設に入居中、介護サービス費や医療費を一定額以上支払ったときに控除が受けられます。
※参照元:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
介護保険の負担限度額認定制度
介護保険の負担限度額認定制度は、住民税非課税の方が介護保険施設に入居したり、介護医療院への入院やショートステイを利用したりする際にかかった食費や居住費を軽減できる制度です。
制度の利用には「介護保険負担限度額認定」を受ける必要があります。次の条件をすべて満たす方が対象となります。(※)
- 本人およびその配偶者が住民税非課税であること
- 本人と住民票上同一世帯の方が住民税非課税であること
- 利用者負担段階ごとに定められた収入・資産要件を満たすこと
制度の対象となる施設のうち、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は対象外です。
※参照元:町田市「「介護保険負担限度額認定制度」について」
https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/kaigo/hutan/hutangendogaku.files/2024futangendogaku.pdf
高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度(高額介護合算療養費制度)は、1年間(8月1日~翌7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計したときに、超過分を払い戻せる制度です。(※)
一例として、世帯全員が市町村民税非課税で、医療保険30万円と介護保険30万円を(計60万円)支払ったときに、申請をすると基準額である31万円のみの支払いにとどまり、超過分の29万円が還付される仕組みです。
※参照元:厚生労働省「高額介護合算療養費制度」https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-29.html
お金がないときにできる対策方法や制度をチェック
今回は、認知症の方が施設に入居する際に、お金がない場合の選び方や利用できる制度を紹介しました。
入居費用を抑えるためには、家賃・管理費が安い施設を選ぶことはもちろんですが、入居一時金がない施設や公的施設・多床室を選ぶ方法もあります。
気になる施設は見学や体験入居を行い、住みやすさをチェックするようにしましょう。施設の立地条件やアクセス、認知症の方へのサポート体制も確認して、満足度の高い施設を選んでみてください。
市川市・浦安市で訪問診療の受診をお考えの方は、
南行徳の面野医院 (訪問診療専用番号 047-321-4600)へご相談ください。
📞047-321-4600からお電話でも受付中(診療時間内)
訪問診療についてのお問い合わせはこちら